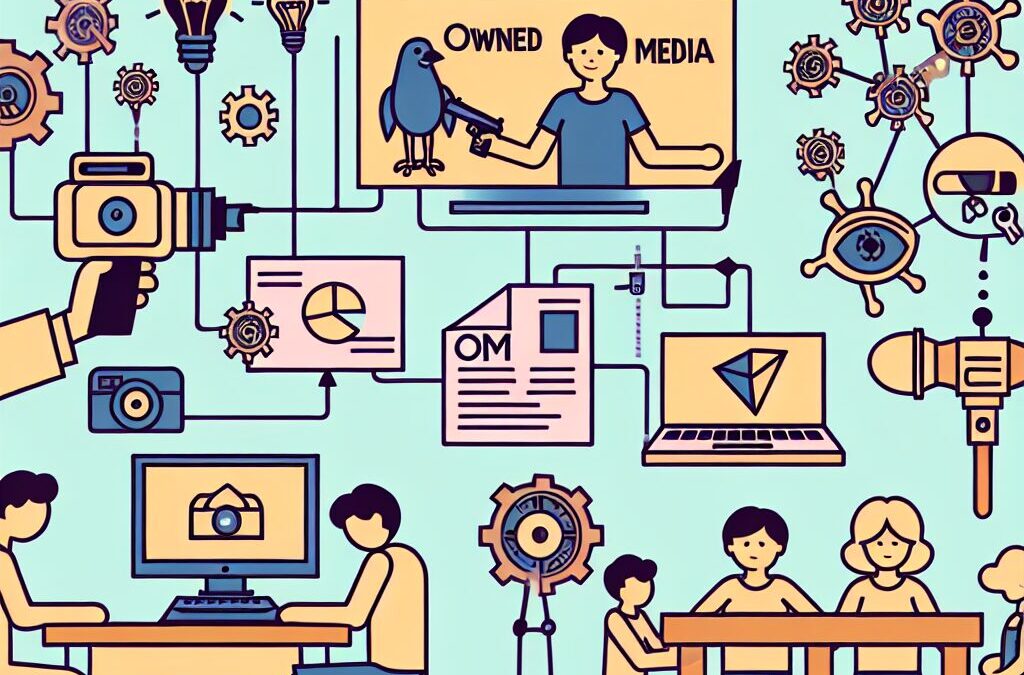「生成AIを導入すれば、記事制作はもっと楽になるはず」──そう期待して始めたものの、品質への不安や成果の頭打ちを感じていませんか。
2024年から2025年にかけて、オウンドメディアを取り巻く環境は大きく変わりました。生成AIの進化により、誰でも一定水準の記事を量産できる一方で、検索結果では“平均的な情報”が埋もれやすくなっています。その結果、これまで通用していたSEO施策や編集体制が、急速に機能しなくなりつつあります。
今、問われているのは「AIを使うかどうか」ではなく、「人とAIをどう協働させ、編集プロセス全体をどう再設計するか」です。本記事では、国内外の調査データや企業事例、SEO・法的観点を踏まえながら、AI時代にオウンドメディアが成果を出し続けるための編集プロセスデザインを体系的に整理します。読み終える頃には、自社メディアで今すぐ見直すべきポイントと、次の一手が明確になるはずです。
生成AIが変えたオウンドメディア運営の前提条件
生成AIの登場によって、オウンドメディア運営の前提条件は根本から書き換えられました。かつては「人手と時間をかけて記事を量産できるか」が競争力でしたが、現在はその前提が成立しません。**平均的な情報を大量に発信するだけでは、価値がほぼゼロになる時代**に入ったからです。
PwCコンサルティングの生成AI実態調査によれば、2025年時点で成果を上げている企業とそうでない企業の差は、ツールの有無ではなく「経営レベルでAI活用を前提に業務を再設計しているか」にあります。特にCAIOを設置している企業では、生成AIを単なる効率化手段ではなく、メディア価値を再定義する基盤として扱っています。
この変化は、コンテンツの希少性構造を一変させました。検索意図を満たす網羅的な説明や一般論は、生成AIが瞬時に作れてしまいます。その結果、**「誰でも書ける情報」は競争力を失い、「そのメディアでしか語れない文脈」だけが評価される**ようになっています。
矢野経済研究所の調査が示すように、生成AIへの投資額は企業間で二極化しています。無料ツールを個人利用する層と、自社データを活用した高度なAI環境を整備する層では、今後アウトプットの質に決定的な差が生まれます。これは努力量ではなく、前提設計の差です。
| 従来の前提 | 生成AI以降の前提 |
|---|---|
| 人が書くこと自体が価値 | 誰が、どんな意図で編集したかが価値 |
| 情報量と更新頻度が重要 | 独自インサイトと信頼性が重要 |
| 制作コストは増えるもの | AI前提で再配分するもの |
LiKGの調査では、長寿オウンドメディアの約半数が月15本以上の記事を公開していますが、同時に現場の疲弊も顕在化しています。ここで重要なのは、AIを「楽をする道具」と捉えるか、「編集思想を進化させる装置」と捉えるかです。前者では品質低下を招き、後者では競争優位が生まれます。
Ideatechの海外調査でも、AIをワークフローに統合した企業の約8割が品質向上を実感しています。ただし、その73%が人間によるレビューを欠かしていません。この事実は、**生成AIが前提となった今も、最終的な価値判断の主体は人である**ことを示しています。
つまり、生成AI時代のオウンドメディア運営とは、「書く能力」を競う世界ではなく、「問いを立て、編集し、責任を持つ能力」を競う世界です。この前提を受け入れられるかどうかが、これからの成長曲線を決定づけます。
国内企業に見る生成AI活用の現状と成果の二極化

国内企業における生成AI活用は、2024年から2025年にかけて急速に進展する一方で、成果面では明確な二極化が生じています。PwCコンサルティングの調査によれば、生成AI導入で「期待以上の成果」を上げている企業と、「期待未満」にとどまる企業の差は、ツール選定以前に経営レベルでの位置づけと投資姿勢にあるとされています。
象徴的なのがCAIO(最高AI責任者)の有無です。成果創出企業では約6割がCAIOを設置しているのに対し、成果が出ていない企業では1割程度にとどまります。生成AIを単なる業務効率化ツールではなく、事業変革や競争優位を生む戦略資産として扱っているかどうかが、オウンドメディアの成果にも直結しています。
| 企業層 | AI投資の特徴 | メディア成果への影響 |
|---|---|---|
| 限定活用層 | 無料版中心・個人利用 | 汎用的な内容に留まり差別化が困難 |
| 戦略投資層 | 有料プラン・API連携 | トンマナ統一と生産性向上を両立 |
矢野経済研究所の調査でも、国内企業の約4割が無料ツールのみを利用している一方、RAGや自社データ連携に投資する企業群が着実に増えていると報告されています。この投資判断の差は、将来的にコンテンツ品質と検索評価の格差として顕在化します。
一方、現場視点では切実な事情もあります。LiKGの実態調査では、長寿オウンドメディアの約半数が月15本以上の記事更新を行っており、担当者の約半数が生成AIを活用しています。しかし活用内容はアイデア出しや下書きに留まり、品質向上まで到達していないケースも少なくありません。
実際、WACULのように構成設計へAIを重点投入した企業では、制作スピードが約2倍、コストは半減しています。Ideatechのレポートでも、AIを統合したマーケティング担当者の79%が品質向上を実感したとされ、適切な役割分担があれば品質は下がらないことが示されています。
国内企業の生成AI活用は、試行段階を抜け、成果創出企業と停滞企業に分かれ始めています。この二極化は一時的なものではなく、オウンドメディアの競争力そのものを左右する構造的な分岐点になりつつあります。
編集プロセスを再設計するための人とAIの役割分担フレームワーク
編集プロセスを再設計する上で重要なのは、作業単位ではなく意思決定の重さに応じて人とAIの役割を切り分けることです。生成AIは文章生成のスピードと網羅性に優れていますが、編集という営みの本質は、何を語り、何を語らないかを判断することにあります。この判断軸を人が握り続けることが、品質と信頼性を両立させる前提条件になります。
PwCの生成AI調査によれば、成果を上げている企業ほどAI活用を現場任せにせず、役割定義を明確に設計しています。特にオウンドメディアでは、Human-in-the-loop型のフレームワークが有効です。これはAIを主体に据えるのではなく、人の判断を必ずループの中心に置く設計思想です。
具体的には、編集プロセスを三つの文脈で整理すると分担が明確になります。第一に企画・構想段階です。このフェーズではAIに大量の選択肢を出させることが有効です。検索意図の洗い出し、競合構成の分析、想定読者の疑問リスト化などはAIが得意とします。一方で、その中から自社が語るべきテーマと切り口を選び取るのは編集者の仕事です。矢野経済研究所の調査が示すように、高度活用企業はここに最も時間を投資しています。
第二に構成・下書き段階です。WACULの事例が示す通り、構成案作成をAIに任せることで制作時間は大幅に短縮されます。ただし、AIが作る構成はあくまで平均解です。**一次情報や独自視点をどこに差し込むか、物語の起点と終点をどう設計するかは人が担う必要があります。**Ideatechのレポートでも、品質向上を実感している企業の多くが人による編集介入を前提にしています。
| 編集文脈 | AIの主な役割 | 人の主な役割 |
|---|---|---|
| 企画・構想 | 選択肢の大量生成、分析 | 切り口の決定、優先順位付け |
| 構成・下書き | 構造化、たたき台作成 | 独自情報の注入、文脈設計 |
| 編集・確認 | 誤り検知、表現改善提案 | 最終判断、責任の所在確定 |
第三に編集・レビュー段階です。AIは誤字脱字や論理の飛躍、表現の偏りを検知する優秀な校正者として機能します。しかし、文化庁のガイドラインが示す通り、著作権や倫理リスクの最終判断は人に帰属します。**誰の名前で公開できるかという覚悟を伴う判断は、AIには委ねられません。**
このフレームワークを導入することで、編集者の役割は「書く人」から「設計し、選び、責任を持つ人」へと進化します。AIは作業量を肩代わりしますが、編集の価値そのものを代替するわけではありません。役割分担を誤らなければ、AIは編集プロセスの質を一段引き上げる強力なパートナーになります。
企画・構成・執筆・編集フェーズ別に見る具体的な協働モデル

企画・構成・執筆・編集という一連の制作工程において、人とAIがどのように協働するかを明確に設計できているかどうかが、AI活用の成果を大きく左右します。PwCの調査でも、成果を上げている企業ほどAIを部分最適ではなく、編集プロセス全体に組み込んでいると指摘されています。
企画フェーズ:発散はAI、決断は人
企画段階では、視野の狭さや思い込みが最大のリスクになります。ここでAIは強力な発散装置として機能します。検索クエリ分析や共起語抽出、ペルソナごとの悩みリスト化などをAIに任せることで、人間だけでは到達できない網羅性を短時間で確保できます。
一方で、どの切り口を選び、どのテーマを捨てるかという意思決定は人の仕事です。自社のブランド戦略や読者との関係性を踏まえた判断は、業務文脈を理解している人間にしかできません。
- AI:検索意図分析、アイデア大量生成、競合構造の可視化
- 人:企画の採否判断、独自性の定義、一次情報の取得計画
構成フェーズ:型はAI、意味づけは人
構成作りでは、AIが検索上位記事の傾向を分析し、ユーザーの疑問を漏れなくカバーする見出し案を提示します。WACULの事例が示す通り、この工程をAI化することで制作時間を半減させても品質を維持できます。
しかし、そのまま採用すると「どこかで見た構成」になりがちです。読者にとっての新しさや文脈的な必然性を与えるのは人の役割です。構成の順序入れ替えや強調ポイントの調整によって、情報に意味を与えていきます。
執筆フェーズ:下書きはAI、物語は人
執筆段階では、AIに一次ドラフトを生成させることで「白紙の恐怖」を排除できます。事実関係や一般論の整理はAIが得意とする領域です。
そこに、取材で得た具体的エピソードや現場感、担当者の言葉を重ねることで初めて、読者の記憶に残る文章になります。Ideatechの調査でも、AIを壁打ち相手として使い、人が加筆することで品質が向上したと感じる担当者が79%に上っています。
編集・確認フェーズ:検知はAI、責任は人
編集工程では、AIが誤字脱字や論理の飛躍、表現上のリスクを検知します。文化庁のガイドラインでも示されている通り、著作権や倫理面のチェックは重要性を増しています。
最終的な公開判断と責任は必ず人が負う必要があります。ハルシネーションの見極めや、自社メディアとしての信頼性担保は、Human-in-the-loopの要となる工程です。
| フェーズ | AIの主な役割 | 人の主な役割 |
|---|---|---|
| 企画 | 発想拡張・網羅的分析 | 意思決定・独自性定義 |
| 構成 | 標準構造の提示 | 文脈設計・強弱調整 |
| 執筆 | 一次ドラフト生成 | 物語化・一次情報加筆 |
| 編集 | リスク検知・改善案提示 | 最終判断・責任所在 |
このようにフェーズごとに役割を固定せず、強みが最大化される配置を行うことが、AI時代の編集プロセス設計における現実的かつ再現性の高い協働モデルです。
SGE時代のSEO戦略と情報ゲインを生むコンテンツ設計
SGEが検索体験の前提となった現在、SEO戦略は「順位を取る技術」から「AIに要約されてもなお価値が残る情報設計」へと進化しています。AI Overviewsは既存情報の平均値を高速で提示しますが、その裏側でGoogleがより強く評価し始めているのが情報ゲインです。
情報ゲインとは、検索ユーザーがそのコンテンツに触れることで、新しい理解や意思決定の変化を得られるかという視点です。Googleの検索品質評価ガイドラインの思想を研究する専門家の分析によれば、SGE環境では「要約できない情報」ほど評価されやすくなる傾向が指摘されています。
情報ゲインを生むコンテンツ設計では、単なる網羅性よりも「差分」が重要です。たとえば用語解説であれば定義を書くのではなく、現場での使われ方の揺れや、導入時につまずきやすいポイントまで踏み込むことで、AI要約との差別化が生まれます。
情報ゲインを高める設計要素
- 自社・自分たちが実際に経験したプロセスや判断理由を含める
- 一般論に対して「なぜそうならないケースがあるのか」を示す
- 数字やフレームワークの背景にある前提条件を言語化する
Ideatechの海外調査では、AIを活用しつつも人間が文脈補足を行ったコンテンツは、そうでないものと比べて「理解が深まった」と評価される割合が約1.4倍高いという結果が示されています。これは情報量ではなく、意味の付加が価値を生んでいる証拠です。
| 設計観点 | 従来SEO | SGE時代 |
|---|---|---|
| 主目的 | 検索順位獲得 | 理解と納得の提供 |
| 評価されやすい要素 | 網羅性・文字数 | 独自視点・判断材料 |
| AIとの関係 | 競合 | 補完・差別化 |
重要なのは、SGEでクリックが減ること自体を悲観しない視点です。SGEで概要を理解した上で、より深い意思決定や具体的検討をしたいユーザーだけがサイトを訪れるため、流入数は減っても質は上がります。実際、国内のBtoBオウンドメディアでは、SGE導入後にセッション数は減少した一方で、資料請求率が向上した事例も報告されています。
そのため編集設計では、「誰が・どの立場で・どんな判断をするための記事か」を明確にし、AI要約の先にある問いに答える構造が求められます。**検索結果で完結しない、思考を一段深めるコンテンツこそが、SGE時代のSEOにおける最大の資産になります。**
E-E-A-Tを高めるために編集者が担うべき判断と責任
生成AIの普及により、コンテンツ制作のスピードと量は飛躍的に向上しました。一方で、**E-E-A-Tを最終的に担保できる存在は、今もこれからも編集者です**。特にExperience(経験)とTrustworthiness(信頼性)は、ツールではなく判断の積み重ねによってのみ成立します。
Googleの検索品質評価ガイドラインにおいても、「誰が、どのような立場と責任でその情報を発信しているか」は重要な評価軸とされています。AIが生成した文章がどれほど流暢であっても、実体験に基づかない一般論や、出典が曖昧な記述は、長期的には評価されません。
編集者が担うべきE-E-A-T判断の中核
- この記事に一次情報や実体験が本当に含まれているか
- 専門家として名前を出せる人物が内容に責任を持てるか
- 読者に誤解や過度な期待を与える表現になっていないか
Ideatechの調査では、AIを活用している企業の73%が「最終的なレビューは人間が行っている」と回答しています。これは、品質管理だけでなく、**責任の所在を明確にするための編集判断が不可欠**であることを示しています。
特に注意すべきは、AIによるハルシネーションです。もっともらしい統計や架空の事例は、専門知識がなければ見抜けません。編集者は、内容の正否だけでなく、「なぜその情報を載せるのか」「載せない判断は妥当か」という編集倫理まで含めて判断する立場にあります。
| 判断領域 | AIが得意 | 編集者の責任 |
|---|---|---|
| 情報収集 | 網羅的な整理 | 信頼できる情報源かの選別 |
| 文章生成 | 構文・表現の最適化 | 文脈と意図の最終調整 |
| 公開判断 | 不可 | 社会的・ブランド的影響の評価 |
PwCの生成AI調査でも、成果を出している企業ほどAI活用を経営・編集判断のレイヤーまで引き上げていることが示されています。現場任せにせず、**編集者が品質と信頼のゲートキーパーになる体制**が、E-E-A-T強化の前提条件です。
AI時代の編集者は、文章を直す人ではありません。情報の重みを測り、経験と専門性を可視化し、読者と社会に対して説明責任を果たす存在です。この役割を自覚し、引き受けられるかどうかが、オウンドメディアの信頼性を左右します。
生成AI活用に伴う著作権リスクとオウンドメディアのガバナンス
生成AIの活用が進むにつれ、オウンドメディア運営において無視できなくなっているのが著作権リスクとガバナンスの問題です。効率化や量産に目を奪われた結果、法的・倫理的な配慮が後回しになると、ブランド毀損や訴訟リスクに直結します。
文化庁が2024年に公表した「AIと著作権に関する考え方」によれば、AI生成物であっても既存著作物との類似性と依拠性が認められれば著作権侵害となり得ます。特に注意すべき点は、**利用者が元ネタを意識していなくても責任を免れない**という解釈です。これはオウンドメディアの編集責任者にとって極めて重い意味を持ちます。
実務で問題になりやすいのが、特定の作家やメディアの文体・構成を強く模倣するプロンプトです。文化庁の整理では、意図的な模倣は依拠性が推認されやすく、企業利用ではリスクが高いとされています。海外では実際に、AI生成コンテンツが既存記事と酷似しているとして削除要請を受けた企業事例も報告されています。
こうしたリスクを抑えるため、ガバナンスの観点では編集プロセスへの統制が不可欠です。PwCの生成AI調査でも、成果を上げている企業ほどガイドラインや責任者を明確にしている傾向が示されています。場当たり的な現場任せではなく、組織的ルールが競争力になります。
| ガバナンス項目 | 具体的な対応例 |
|---|---|
| プロンプト管理 | 作家名・作品名の模倣指示を禁止し、トーンや目的で指定 |
| チェック体制 | 公開前に剽窃チェックツールと人の目で確認 |
| 責任の所在 | 編集長またはAI責任者が最終承認 |
さらに重要なのがHuman-in-the-loopの徹底です。Ideatechのレポートでも、AI活用企業の73%が人によるレビューを必須としており、これが品質と法的安全性の両立につながっています。**AI生成文をそのまま公開しない**という原則は、ガバナンスの最低条件といえます。
オウンドメディアは企業の公式な発信装置です。生成AIを使うからこそ、著作権への理解と統制された編集ガバナンスが、読者からの信頼を守る最後の防波堤になります。
AIでは代替できない暗黙知を競争力に変える組織づくり
生成AIが平均点のアウトプットを高速で量産できる時代において、組織の競争力を決定づけるのは、人にしか扱えない暗黙知をいかに活用できるかです。暗黙知とは、マニュアル化されていない現場感覚や判断の勘所、失敗から得た教訓の蓄積を指します。AIでは代替できない価値は、個人の頭の中ではなく、組織の仕組みとして保持されているかどうかで差がつきます。
PwCの生成AI調査でも、成果を上げている企業ほどAI活用を個人任せにせず、組織的に知見を集約している点が指摘されています。オウンドメディアにおいても、編集者やライター個人の経験に依存する状態では、退職や異動とともに価値が失われてしまいます。そこで重要になるのが、暗黙知を引き出し、共有し、再利用できる編集組織の設計です。
具体的には、企画会議や記事レビューの場で「なぜその構成にしたのか」「なぜこの表現を避けたのか」といった判断理由を必ず言語化し、議事録やコメントとして蓄積します。これらは完成原稿以上に価値のある情報であり、後からAIに参照させることで、表層的ではない自社らしいアウトプットを生み出す土台になります。MOLTSが提唱する暗黙知の形式知化モデルでも、判断背景の記録が最重要要素とされています。
また、暗黙知は成功事例だけでなく失敗事例に宿ります。LiKGの調査で指摘されているように、品質に悩むメディアほど失敗の共有が行われていません。検索順位が伸びなかった記事、炎上しかけた表現、読者に誤解された構成などを定期的に振り返り、編集ノートとして残すことで、組織全体の学習速度が高まります。
| 暗黙知の種類 | 具体例 | 組織化の方法 |
|---|---|---|
| 企画判断 | 読者ニーズの見極め | 企画理由の記録 |
| 表現感覚 | 炎上回避の言い回し | 修正履歴の共有 |
| 編集勘 | 構成の良し悪し | レビューコメント蓄積 |
さらに、暗黙知を競争力に変えるには心理的安全性も欠かせません。なぜなら、暗黙知は「迷い」や「違和感」といった未整理な状態で語られることが多く、正解だけを求める文化では表に出てこないからです。baigieがUXの文脈で強調するように、意見を出しやすい環境設計は、編集組織にもそのまま当てはまります。
生成AIは、この暗黙知を拡張するパートナーとして機能します。人が蓄積した判断プロセスや背景情報を参照させることで、AIは単なる文章生成装置から、自社の思考様式を反映した編集アシスタントへと進化します。AIでは代替できない暗黙知を、AIと共に増幅させる組織づくりこそが、これからのオウンドメディアの本質的な競争力になります。
目的別に考えるAIライティングツール選定と活用の視点
AIライティングツールを選定する際に最も重要なのは、機能の多さや流行ではなく、**「自社のオウンドメディアで何を達成したいのか」という目的から逆算する視点**です。PwCの調査でも、生成AI活用で成果を上げている企業ほど、AIを戦略目的にひもづけて導入していることが示されています。目的が曖昧なままでは、どれほど高性能なツールを導入しても現場で定着せず、期待外れに終わります。
目的別に見ると、AIライティングツールは大きく役割が分かれます。例えば「企画や構成の質を高めたい」のか、「SEOでの網羅性を担保したい」のか、「量産で更新頻度を維持したい」のかで、最適解はまったく異なります。ITreviewなどのレビュー分析でも、満足度が高い企業ほど用途を限定してツールを使い分けています。
| 目的 | 適したツールタイプ | 活用のポイント |
|---|---|---|
| 企画・構成の高度化 | 汎用対話型AI | 検索意図分析や切り口の壁打ちに使い、人が最終判断を行う |
| SEO品質の安定化 | SEO特化型AI | 競合比較や網羅性チェックに限定して活用する |
| 更新頻度の維持 | 記事量産特化型AI | ドラフト生成までに留め、編集で独自性を加える |
特に注意したいのは、「万能ツール1本で全工程を回そう」とする発想です。Ideatechの海外調査によれば、AI導入で品質向上を実感している企業の73%は、人間によるレビューを必須プロセスに組み込んでいます。これは、ツール選定がそのまま編集プロセス設計と直結していることを意味します。
また、ツール活用の巧拙はUIや運用設計にも左右されます。baigieが指摘するように、操作が複雑なツールほど現場で敬遠されがちです。実際、無料の汎用AIだけを個人利用している企業では、セキュリティ制約により本格活用に至らないケースが多いと矢野経済研究所も報告しています。
そのため、目的別にツールを整理したうえで、「誰が・どの工程で・何のために使うのか」を明文化し、プロンプトや使い方をテンプレート化することが重要です。AI時代のツール選定とは、単なるソフト選びではなく、オウンドメディアの成果を左右する編集戦略そのものだといえます。