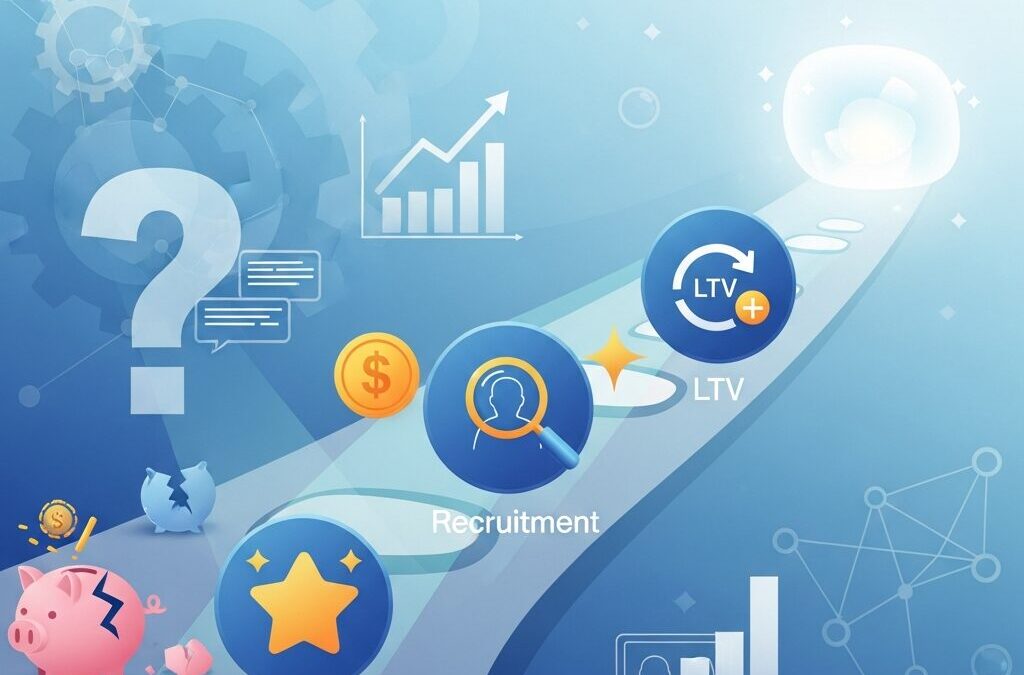オウンドメディアを運営しているものの、「社内で正当に評価されない」「予算が取りづらい」「成果を説明できない」と悩んでいませんか。
広告費の高騰やサードパーティクッキー規制、生成AIによる検索体験の変化など、外部環境は確実にオウンドメディアに追い風をもたらしています。それにもかかわらず、現場では評価と実感がかみ合わないケースが後を絶ちません。
その原因は、コンテンツの質やSEOテクニック以前に、「成果の定義」と「社内への伝え方」にあります。PVや記事本数といった媒体指標だけでは、経営層が求める事業成果と接続できないのです。
本記事では、オウンドメディアを単なる情報発信の場ではなく、売上・採用・ブランド・LTVに貢献する事業資産として再定義します。最新データや先進企業の事例、専門家の知見をもとに、経営層を納得させ、継続投資を勝ち取るための考え方と全体像を整理します。
評価されない状況から抜け出し、オウンドメディアを企業成長の中核に据えたい方にとって、実践の指針となる内容をお届けします。
2026年のデジタル環境変化とオウンドメディア再評価の必然性
2026年に向けてデジタル環境は明確な転換点を迎えています。サードパーティクッキーの規制強化により、従来のリターゲティング広告は精度を失い、実際に多くの企業でCPAが上昇しています。さらに、Googleが推進するSGEをはじめとした生成AIによる検索体験の進化は、検索結果画面そのものを情報取得の最終地点に変えつつあります。**広告と検索という外部プラットフォームに依存した集客モデルは、構造的に不安定な時代に入った**といえます。
この環境下で再評価されているのが、企業が自らコントロールできるオウンドメディアです。Googleや業界の研究者が繰り返し指摘している通り、今後のデジタルマーケティングではFirst Party Dataの保有と活用が競争力の源泉になります。オウンドメディアは単なる情報発信チャネルではなく、顧客の行動履歴や関心を蓄積できる数少ない接点であり、**アルゴリズム変更の影響を最小化できる自社資産**です。
一方で、生成AIの普及は「オウンドメディア不要論」を生みやすい側面もあります。誰でも短時間で文章を生成できるようになった結果、汎用的な解説コンテンツの価値は相対的に低下しています。しかし、検索体験の調査や専門家の見解によれば、AIが参照・要約する情報の多くは信頼性の高い一次情報に依存しています。**つまり、AI時代であっても、独自性と信頼性を備えたオウンドメディアは、むしろ情報供給源として重要性を増している**のです。
| 環境変化 | 従来モデルへの影響 | オウンドメディアの価値 |
|---|---|---|
| 3rdパーティクッキー規制 | 広告効果の不安定化 | 自社データによる継続的接点 |
| 生成AI検索の普及 | 流入数の減少リスク | 信頼できる一次情報源 |
| 広告費高騰 | ROIの悪化 | 中長期での獲得コスト低減 |
実際、複数の実態調査では、企業のマーケティング責任者の間で「外部依存の限界」を感じる声が増えています。短期的な数値が出やすい広告施策と異なり、オウンドメディアは成果が見えにくいという課題を抱えますが、**不確実性が高まるほど、再現性と蓄積性を持つ施策の価値は上がる**というのが経営視点での合理的な判断です。
2026年のデジタル環境変化は、オウンドメディアを「やるかどうか」の選択肢から外し、「どう位置づけ、どう育てるか」を問うフェーズに押し上げています。短期成果に左右されやすい外部チャネルと異なり、オウンドメディアは時間とともに信頼とデータを積み上げる事業資産です。**この構造的価値を理解し直すこと自体が、再評価の必然性**だといえるでしょう。
オウンドメディアが社内で評価されない構造的な理由

オウンドメディアが社内で評価されない最大の理由は、成果そのものではなく、成果の捉え方が組織構造と噛み合っていない点にあります。多くの企業では、経営層が重視するのは短期の売上や利益であり、四半期単位でPLにどう寄与したかが判断基準になります。一方、オウンドメディアは中長期で効いてくる「資産形成型」の施策であり、この時間軸のズレが評価の断絶を生みます。
広告は投下額と成果が比較的直線的に結びつくため、経営層にとって理解しやすい投資です。これに対し、オウンドメディアは成果が段階的かつ間接的に現れます。検索順位の上昇、指名検索の増加、検討期間の短縮などは、売上に影響していても即座に数字として現れにくく、「効いているが見えない」状態に陥りがちです。
2024年の『広報会議』調査でも、担当者の8割以上が効果を実感している一方で、その多くが「企業イメージ向上」といった定性的評価に留まっていました。経営層の意思決定に必要な定量データへ翻訳されない限り、評価対象になりにくいのが現実です。
| 視点 | 経営層の期待 | オウンドメディアの実態 |
|---|---|---|
| 時間軸 | 短期(四半期) | 中長期(半年〜数年) |
| 成果指標 | 売上・利益 | 検索流入、接触回数、信頼形成 |
| 因果関係 | 単純で即時的 | 複合的で遅行 |
さらに構造的な問題として、評価指標の設計段階に経営が関与していない点も見逃せません。現場はPVや記事本数といった媒体指標を追いがちですが、これらは事業成果と直結しません。結果として「数字は伸びているが意味が分からない」という印象を与え、評価が宙に浮きます。
株式会社検索順位の海賊の分析によれば、オウンドメディアが継続できない企業ほど、KGIが売上と紐づいておらず、撤退基準も曖昧です。終わりが見えない投資は、経営にとって最もリスクが高く、評価を下げる要因になります。
もう一つの構造的理由は、オウンドメディアが「誰の責任か」不明確なまま運用されていることです。複数部署が関与しながら最終責任者が定まらない場合、成果は分散し、失敗の責任だけが強調されます。組織論的に見ると、これは評価されない施策の典型です。
つまり、オウンドメディアが評価されないのは能力不足ではなく、評価されにくい構造の中で運用されているからです。この構造を理解せずに改善を試みても、担当者の努力は報われません。まず必要なのは、成果が正しく認識されない理由を、組織の視点から言語化することです。
PV至上主義の限界と成果定義のズレ
オウンドメディアが正当に評価されない最大の要因の一つが、PV至上主義に基づく成果定義のズレです。PVは確かに分かりやすく、誰にでも説明しやすい指標ですが、事業成果そのものを示す指標ではありません。ページが多く閲覧された事実と、売上や受注、採用、ブランド選好といった経営成果の間には、必ずしも直接的な因果関係が存在しないからです。
実際、広報会議が2024年に実施した調査でも、オウンドメディアの効果として「企業イメージ向上」を実感している担当者は7割を超える一方で、その効果を定量的に説明できているケースは限られていました。PVが伸びているにもかかわらず評価されない背景には、経営層が見ている成果と、現場が報告している指標が噛み合っていないという構造的問題があります。
このズレは、マーケティングの時間軸にも起因します。PVは短期で増減が見える指標ですが、オウンドメディアの本質は中長期で蓄積されるストック型資産です。Googleの検索品質評価ガイドラインが示すように、専門性や信頼性は一朝一夕では構築できません。それにもかかわらず、四半期単位の会議でPVだけを問われ続ければ、更新のための更新に陥るのは必然です。
| 視点 | PV中心の評価 | 事業視点の評価 |
|---|---|---|
| 指標の性質 | 量的・短期 | 質的・中長期 |
| 説明対象 | マーケティング内部 | 経営層・他部門 |
| 判断材料 | アクセス数 | 売上貢献・コスト削減・意思決定支援 |
さらに問題なのは、PVが増えても成果が出ない場合、その責任が現場に一方的に帰されやすい点です。ラストクリックのみを成果とみなす評価では、比較検討段階で機能する記事の価値が可視化されません。プロフェッショナル向けマーケティング分析では、アシストコンバージョンの重要性が以前から指摘されており、これはGoogle Analytics 4の設計思想にも反映されています。
PVはあくまで入口の指標であり、ゴールではありません。にもかかわらず、PVをKGIに置いた瞬間、メディアの目的は事業貢献から乖離します。この成果定義のズレを放置したままでは、どれだけ良質なコンテンツを積み上げても「数字は出ているが意味がない」という評価から抜け出せません。評価の物差しを変えない限り、オウンドメディアは永遠にコストセンターのままです。
事業成果につなげる多層的KPI設計の考え方
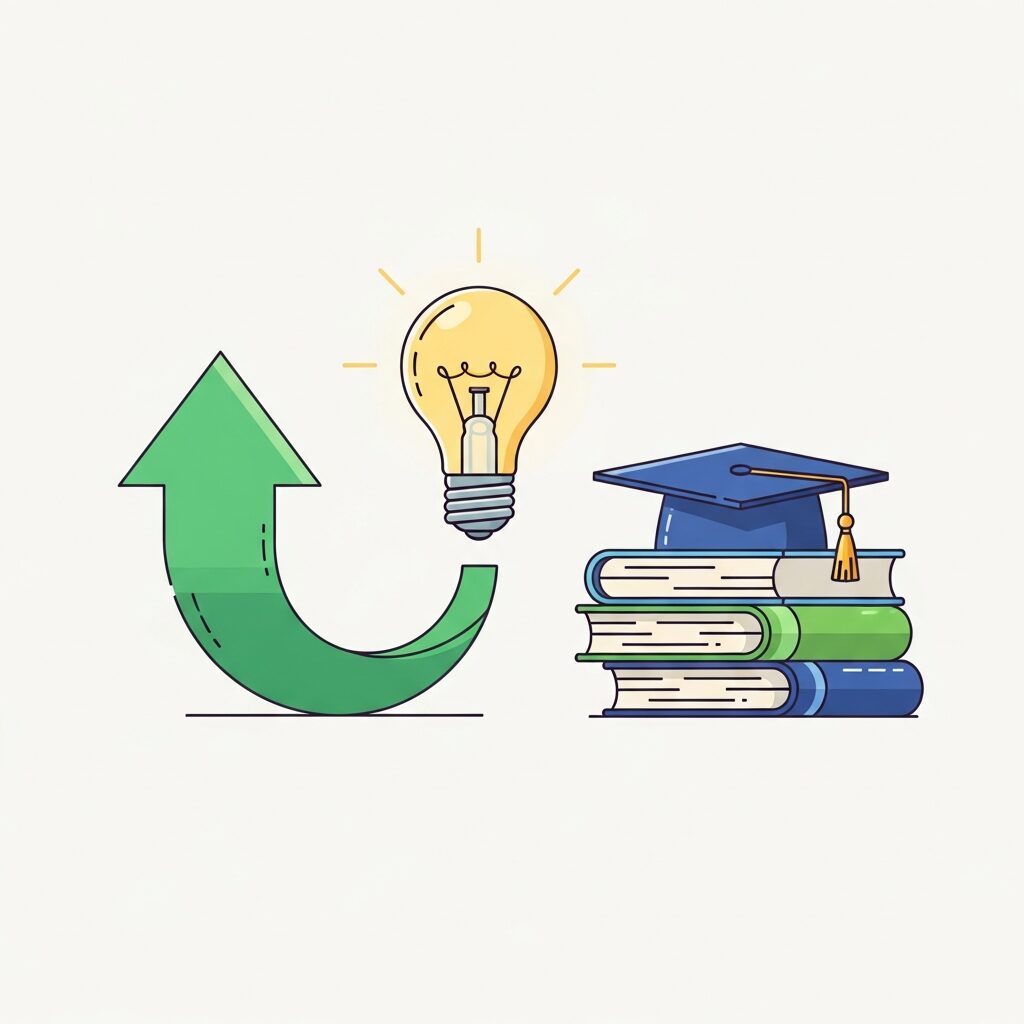
事業成果につなげるためには、オウンドメディアのKPIを単一指標で管理しないことが重要です。特にPVやセッション数だけを追う設計では、経営層が求める事業インパクトと結びつかず、評価の断絶が生まれやすくなります。**KPIは事業成果から逆算し、時間軸と役割の異なる複数レイヤーで設計する必要があります。**
この考え方は、ハーバード・ビジネス・レビューでも繰り返し指摘されている「リーディング指標とラギング指標の分離」に近いものです。売上や利益は最終的な結果指標であり、そこに至るまでのプロセスを可視化する中間KPIがなければ、施策の良し悪しを途中で判断できません。オウンドメディアは特に成果が遅行しやすいため、多層的なKPI設計が不可欠です。
具体的には、短期・中期・長期という時間軸で役割を分けて指標を置くことで、経営と現場の会話が成立しやすくなります。短期では行動変化、中期では商談や指名、長期ではLTVやコスト構造への影響を捉えます。**この階段構造があることで、「今は仕込みの段階である」という説明がロジックとして成立します。**
| レイヤー | 主なKPI例 | 事業との接続点 |
|---|---|---|
| 短期(行動) | 再訪率、滞在時間、特定記事の完読率 | 課題理解・検討度の深化 |
| 中期(機会) | アシストCV、指名検索数、資料請求率 | 商談創出・広告効率改善 |
| 長期(成果) | LTV、CAC、受注率 | 利益率・事業成長 |
例えばB2B企業の場合、GA4やMAツールを用いて「特定の記事を読んだユーザーは、読んでいないユーザーに比べて商談化率が高い」という差分を示すことで、PVでは見えなかった価値が可視化されます。Content Marketing Instituteによれば、ROIを測定できている企業ほど、予算継続率が高い傾向にありますが、その前提にはこのような中間KPIの存在があります。
また、多層的KPIは社内合意形成の装置としても機能します。営業部門には商談化や受注率、人事部門には採用単価や応募質、経営層にはCACやLTVといった、それぞれの関心軸に翻訳できる指標を用意することで、オウンドメディアは部門横断の事業資産として認識されやすくなります。**KPI設計とは測定の技術ではなく、社内で価値を共有するための設計図です。**
重要なのは、すべてを一度に完璧に測ろうとしないことです。最初は仮説ベースでも構わないため、事業成果に近い指標との因果関係を示し続けることが、評価を積み上げる最短ルートになります。その積み重ねこそが、オウンドメディアをコストではなく投資として位置づける根拠になります。
ブランド資産としての価値を数値で示す方法
オウンドメディアを事業資産として評価してもらうためには、「ブランド価値」という曖昧な概念を、経営層が意思決定に使える数値へと変換する必要があります。重要なのは、好意的な反応や手応えを感覚で語るのではなく、比較可能で再現性のある指標として示すことです。その代表的な方法が、広告業界で確立されてきたブランドリフトの考え方を、オウンドメディア評価に応用するアプローチです。
ブランドリフトとは、特定の接触体験がユーザーの認知や態度にどの程度影響を与えたかを測定する手法です。GoogleやMetaなどのプラットフォームが提供する調査設計は、学術的にも広告実務的にも広く利用されており、主観を排した比較が可能です。これをオウンドメディアに転用すると、「記事を読んだ人」と「読んでいない人」の差分を明確に示せます。
| 測定観点 | 具体指標 | 数値化した際の意味 |
|---|---|---|
| 認知 | ブランド認知率 | 市場での想起確率の向上 |
| 態度 | 好意度・信頼度 | 比較検討時の優先順位上昇 |
| 行動意向 | 購入・問い合わせ意向 | 将来売上の先行指標 |
たとえばインバナーサーベイを用い、記事閲覧後に簡易アンケートを表示すると、「当社サービスを検討したい」と回答した割合を非閲覧者と比較できます。ブランドリフト調査を多数分析してきた電通やGoogleの知見によれば、意向の数ポイントの差は、実売上では二桁成長に相当するケースも珍しくありません。この差分こそが、オウンドメディアが生み出したブランド資産の増分です。
さらに実務的で経営層に刺さりやすい指標が、指名検索数の増加です。サーチリフト調査として、特定期間における社名やサービス名の検索回数を追うことで、メディア接触がどれだけ「思い出されやすさ」を高めたかを示せます。Googleの公開データでも、指名検索は購買直前行動と強い相関があるとされています。
指名検索が増えるということは、将来の広告コストが下がることを意味します。なぜなら指名キーワードはクリック単価が低く、競合入札も起きにくいためです。結果として、ブランド資産の蓄積は、PL上では広告費削減という形で顕在化します。このロジックはCFOや経営企画部門とも共通言語になりやすい点が特長です。
もう一段踏み込むなら、ブランドリフトとLTVを結びつけます。記事を複数回閲覧したユーザーとそうでないユーザーで、平均購入単価や継続率を比較すると、ブランド理解が深い顧客ほど長期的な収益性が高いことが見えてきます。これはContent Marketing Instituteなども一貫して示している傾向です。
このように、ブランド資産は「測れない無形資産」ではありません。調査設計と指標の置き方次第で、認知・態度・行動・コスト削減まで一貫して数値化できます。オウンドメディア担当者に求められるのは、記事の出来不出来を語ることではなく、ブランド価値がどれだけ事業の将来キャッシュフローを押し上げたかを説明することです。その視点を持った瞬間、メディアは評価される資産へと変わります。
マーケティングを超える部門横断型オウンドメディア活用
オウンドメディアの価値を最大化するためには、マーケティング部門内の成果最適化にとどめず、組織全体の課題解決にどう貢献するかという視点が不可欠です。部門横断型で活用されるオウンドメディアは、単なる集客装置ではなく、社内共通の事業インフラとして機能し始めます。
この発想転換が重要になる背景には、企業価値評価の軸が「短期売上」から「非財務資本」へと広がっている潮流があります。世界経済フォーラムや経済産業省の議論でも、人的資本や関係資本の可視化が中長期的な競争力に直結すると繰り返し示されています。
その中でオウンドメディアは、部門ごとに分断されがちな情報やストーリーを一つの文脈で束ねる役割を担います。例えば人事部門にとっては、採用サイトでは伝えきれない現場の価値観や仕事のリアルを補完する場になります。
実際、米LinkedInのタレントトレンド調査では、求職者の約7割が応募前に企業のストーリーや社員の声を確認すると報告されています。オウンドメディア経由で企業理解が深まった候補者は、内定承諾率や定着率が高まる傾向があり、結果として採用コストの圧縮に寄与します。
| 活用部門 | 主な目的 | 事業インパクト |
|---|---|---|
| 人事・採用 | カルチャー理解の促進 | 採用単価低減・離職率改善 |
| 営業 | 顧客理解の深化 | 商談化率・受注率向上 |
| IR・広報 | 非財務情報の開示 | 企業価値・信頼性向上 |
営業部門との連携も極めて重要です。HubSpotが発表した日本の営業実態調査によれば、営業担当者の多くが「顧客に提供できる有益な情報不足」を課題に挙げています。ここでオウンドメディアの記事が、事例解説や比較検討材料として活用されると、説明工数が削減され、商談の質が向上します。
マーケティングが作ったコンテンツが、営業現場で“使われる”状態になった瞬間、オウンドメディアはコストではなく投資として認識され始めます。これは部門横断型活用の象徴的な変化です。
さらにIRや広報の文脈では、決算資料だけでは伝わらない経営の意思や事業の背景を補足するメディアとして機能します。日本取引所グループが示すコーポレートガバナンス・コードでも、ステークホルダーとの建設的な対話の重要性が強調されています。
オウンドメディアを通じて継続的に発信されるストーリーは、投資家や取引先に対する理解促進につながり、企業全体の信頼残高を積み上げる資産となります。マーケティングを超え、組織を横断して価値を生み出す設計こそが、これからのオウンドメディアに求められる姿です。
生成AI時代におけるコンテンツ戦略と人の役割
生成AIの急速な普及により、コンテンツ制作は「誰でも・早く・安く」できる時代に入りました。HubSpotが2024年に発表した調査によれば、日本のマーケターの8割以上が生成AIを業務に活用しており、その多くが効率化の効果を実感しています。一方で、同調査ではAI活用に対する不安として「内容が画一的になる」「信頼性が担保できない」といった声も多く挙がっています。**生成AI時代のコンテンツ戦略の本質は、効率化そのものではなく、人がどこで価値を発揮するかを再定義する点にあります。**
検索体験の変化も、この再定義を加速させています。Googleが推進するSGEのように、検索結果画面上で要点が要約される環境では、単なる定義解説や一般論はクリックされにくくなります。つまり、AIが代替できる情報は流通価値が下がり、**一次情報や文脈を伴う知見こそが競争優位になる**構造が明確になっています。Google自身もE-E-A-Tの中で「Experience」を重視しており、実体験に基づく語りが評価されやすいことを示唆しています。
この前提に立つと、生成AIと人の役割分担は次のように整理できます。
| 領域 | 生成AIが担う役割 | 人が担う役割 |
|---|---|---|
| 企画・構成 | 検索意図整理、構成案の高速生成 | 事業戦略との接続、優先順位判断 |
| 執筆 | 一次ドラフト、要約、リライト提案 | 体験談、専門的洞察、意思の注入 |
| 品質管理 | 誤字脱字チェック、表現の均質化 | 事実確認、倫理判断、最終責任 |
このハイブリッドモデルを採用することで、制作工数を30〜50%削減しつつ、質を落とさない体制が現実的になります。ただし重要なのは、**人の関与が減るのではなく、関与するポイントが上流化・高度化する**点です。取材設計や問いの立て方、社内専門家からどの視点を引き出すかといった判断は、AIには代替できません。
また、ゼロクリック検索が常態化する中で、オウンドメディアの役割は「流入を稼ぐ場」から「指名される理由を蓄積する場」へと変わります。徳力基彦氏が指摘するように、これからのメディア価値はPVではなく、どれだけ記憶に残り、語られるかにあります。社員の失敗談や意思決定の背景、顧客との葛藤といった生々しい情報は、AI要約では代替できず、ブランドへの信頼を形成します。
経営層への説明においても、「AIでコストを下げました」だけでは不十分です。**AIで捻出した時間を使い、人にしか書けないコンテンツへ再投資している**というストーリーが必要です。結果として指名検索が増え、広告依存が下がり、採用や営業で語られる材料が増える。この因果関係を示すことで、生成AI活用は単なる効率化施策ではなく、事業資産を強化する戦略的投資として位置づけられます。
生成AI時代のコンテンツ戦略とは、人を不要にすることではありません。むしろ、**人の思想、経験、覚悟を際立たせるためにAIを使う**という逆転の発想こそが、オウンドメディアを埋没から救い、長期的な競争力をもたらします。
成功企業に学ぶオウンドメディア成果の捉え方
成功している企業のオウンドメディアに共通するのは、成果を単一の指標で捉えていない点です。彼らはPVや記事本数といった媒体指標ではなく、**事業のどの価値を、どの時間軸で支えているか**という視点で成果を定義しています。この違いが、社内評価と継続投資を大きく左右します。
代表的な例が、クラシコム社が運営する「北欧、暮らしの道具店」です。同社はオウンドメディアを集客装置としてではなく、世界観を共有する顧客との関係資産と位置づけています。決算資料でも重視されているのはPVではなく、エンゲージメントアカウント数やリピート購入率です。**メディアへの接触が、顧客の継続購入と利益率の安定に寄与している**という因果関係を、経営指標で語っている点が特徴です。
このような企業では、成果の捉え方が「短期の売上」か「中長期の資産形成」かで明確に分かれています。オウンドメディアは後者に属するため、広告と同じ物差しで評価しないという合意が、経営レベルで形成されています。
| 企業タイプ | 主な成果指標 | 経営への説明軸 |
|---|---|---|
| BtoC・D2C | リピート率、LTV | 利益率の安定、広告依存の低減 |
| BtoB | 商談化率、受注率 | 営業効率の改善、CAC低減 |
| 共通 | 指名検索数 | ブランド資産の蓄積 |
BtoB領域でも同様です。MOLTSの事例に見られるように、検索上位を獲得した記事を「無料で保有する広告枠」と再定義し、広告換算価値で成果を示しています。月間検索数と想定CPCから算出される金額は、**CFOや経営層にとって理解しやすい成果表現**です。さらに、検索経由リードは受注率が高いという傾向を示すことで、質の違いまで含めて評価しています。
重要なのは、成功企業が必ず「翻訳」を行っている点です。マーケティングの成果を、売上、コスト削減、利益率、リスク耐性といった経営の言語に置き換えています。GoogleやContent Marketing Instituteが示すように、ROIやLTVの観点で語られた施策は、単なる施策報告ではなく投資判断の材料になります。
成功企業に学ぶべき成果の捉え方とは、オウンドメディアを運用成果ではなく、**事業を前進させる構造的な力として測ること**です。その視点を持てた瞬間から、オウンドメディアは評価されない存在ではなく、手放せない事業資産へと変わっていきます。
社内評価を変えるために担当者が取るべき次の一手
社内評価を変えるために担当者が取るべき次の一手は、施策そのものを増やすことではなく、成果の語り方と見せ方を意図的に設計し直すことです。多くの現場では、良質なコンテンツや一定の成果が出ているにもかかわらず、それが経営層に届く手前で価値を失っています。原因はシンプルで、評価者が意思決定に使う文脈に翻訳されていないからです。
まず着手すべきは、報告単位の変更です。PVや記事本数といった媒体指標を主語にする報告は、経営層にとっては判断材料になりません。必要なのは、オウンドメディアを一つの「事業施策」として扱い、売上・コスト・リスク低減のいずれにどう寄与したのかを一本のストーリーで示すことです。これはCMIやSitecoreが提唱するROI思考とも一致しています。
具体的には、月次・四半期レポートの構成を固定化し、毎回同じ軸で語ることが重要です。評価者は比較できない施策を信用しません。以下は、評価を変えやすい報告軸の整理例です。
| 観点 | 示す指標 | 評価者の理解 |
|---|---|---|
| 収益貢献 | アシストCV数、推定売上 | 売上に近い活動か |
| コスト代替 | 広告換算価値、CAC変化 | 費用削減になっているか |
| 将来価値 | 指名検索数、再訪率 | 資産として積み上がるか |
このとき重要なのは、数値の正確さ以上に一貫したロジックです。例えば「この記事を起点に商談化した案件が3件あり、平均受注単価から逆算すると将来売上は約◯◯円規模になる」といった仮説ベースの提示でも構いません。GoogleアナリティクスやMAツールを用いたアトリビューション分析は、その裏付けとして十分に機能します。
次に取るべき一手は、評価者を一人にしないことです。営業、人事、広報といった他部門にとって意味のある成果を意図的に作り、その声を第三者評価として経営層に届けます。心理学で言われるウィンザー効果の通り、自分で語る成果より、他部署から語られる成果の方が評価は跳ね上がります。HubSpotの調査が示すように、部門連携が取れている組織ほど成果創出の再現性は高まります。
最後に、あえて「次の判断ライン」を提示することも有効です。Search Engine Piratesが指摘するように、撤退基準を明示する姿勢は、投資判断の不確実性を下げます。いつまでも続く施策ではなく、期限付きで成果を検証する事業投資として位置付けることで、担当者は説明責任を果たしつつ裁量を獲得できます。
社内評価は、努力や熱量ではなく、理解可能な形で示された価値によって決まります。次の一手とは、新しい企画ではなく、オウンドメディアを事業の言葉で語り直す行為そのものです。
参考文献
- 検索順位の海賊:オウンドメディアが継続できない理由|戦略があれど実行されない
- 広報会議(AdverTimes):オウンドメディア実態調査「企業イメージ向上」に寄与、課題は…
- ProFuture:オウンドメディアの効果はどう分析したらいい?データ分析を徹底解説
- SE Design:ブランドリフトとは?ブランディング広告の成果を客観的に調査する方法
- note pro:ファンを生み出すIRの可能性とは? #等身大の企業広報
- HubSpot(PR TIMES):日本の営業に関する意識・実態調査2024の結果をHubSpotが発表