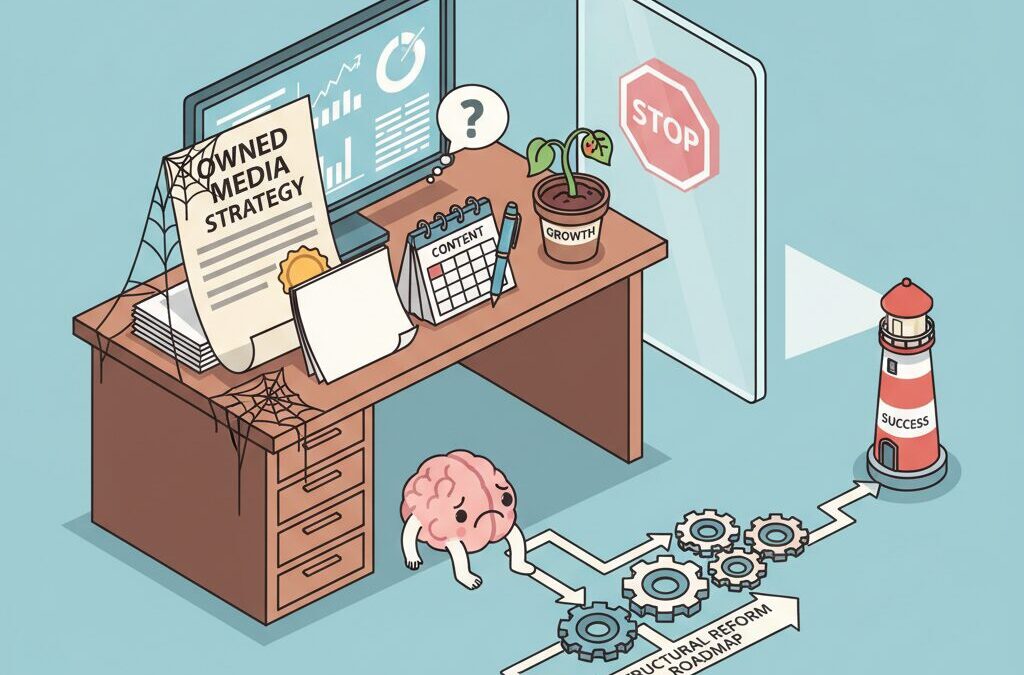オウンドメディアは重要だと分かっているのに、なぜか更新が止まってしまう。立派な企画書や戦略資料はあるのに、記事が増えず、成果も見えない。そんな悩みを抱えていませんか。実はこの状態は個人の努力不足ではなく、多くの企業が陥る「構造的な問題」が原因です。
広告費が高騰し、クッキーレス時代が進む中で、オウンドメディアは企業にとって欠かせない資産になっています。一方で、現場ではリソース不足や属人化、社内調整の難しさなど、理想と現実のギャップに苦しむ声が後を絶ちません。その結果、計画だけが存在し、実行されない「机上メディア」が生まれています。
本記事では、オウンドメディアが実行不全に陥る理由を組織・戦略・心理の観点から整理し、どうすれば継続的に成果を出せる体制へ転換できるのかを解説します。生成AIやKPI設計、先進企業の事例も交えながら、明日から見直すべきポイントが分かる内容です。読み終えたとき、自社メディアの次の一手がきっと見えてくるはずです。
オウンドメディアが抱える「計画と実行」の断絶とは
オウンドメディア運営で最初につまずきやすいのが、計画と実行の間に横たわる深い溝です。多くの企業では、立派な企画書やロードマップが作られる一方で、記事が公開されない、数か月で更新が止まるといった事態が頻発します。この状態は単なる失敗ではなく、構造的な断絶として捉える必要があります。
近年の調査でも、この断絶は数字として表れています。宣伝会議が実施したオウンドメディア活用に関する調査では、約8割の企業が効果を実感していると回答する一方、現場レベルではコンテンツ数の維持や制作リソース不足が最大の課題として挙げられています。つまり、価値は理解されているのに、動かし続ける力が伴っていないという矛盾が常態化しているのです。
この問題を理解する鍵が、「机上メディア」という概念です。戦略的には正しく、方向性も合意されているにもかかわらず、実行段階で止まってしまうメディアを指します。ここで重要なのは、原因を担当者の能力や熱意に求めないことです。断絶の正体は、計画が実行を前提に設計されていない点にあります。
| 計画フェーズで語られること | 実行フェーズで直面する現実 |
|---|---|
| 理想的なKPIや成長曲線 | 日々の執筆時間が確保できない |
| 中長期のブランド価値 | 短期的な成果を求める圧力 |
| 網羅的なテーマ設計 | ネタ切れと他部署協力の欠如 |
このギャップが生まれる背景には、日本企業特有の意思決定構造も影響しています。稟議を通すために計画は精緻になりますが、承認後の運用設計や人員配置は曖昧なまま進みがちです。その結果、オウンドメディアは「始めること」がゴールになり、「続けること」が後回しにされます。
さらに、SEOやコンテンツマーケティングの成果には時間がかかるという特性も断絶を広げます。一般に検索流入が安定するまでには数か月から半年以上を要しますが、広告の即効性に慣れた組織では、その待ち時間が許容されません。計画段階で想定されていた時間軸と、実行段階で求められる成果スピードが噛み合わないのです。
こうした断絶を放置すると、現場は疲弊し、計画は形骸化します。オウンドメディアが計画倒れに終わるかどうかは、戦略の巧拙よりも、この計画と実行の溝を最初にどれだけ現実的に埋められるかにかかっています。ここを直視することが、すべての出発点になります。
『机上メディア』が生まれる背景と日本企業特有の課題

「机上メディア」が生まれる背景には、オウンドメディアの重要性が理解されているにもかかわらず、実行が伴わないという日本企業特有の構造的課題があります。株式会社宣伝会議の調査によれば、約8割の企業がオウンドメディアにプラスの効果を感じていると回答しています。それでも多くの現場で、企画書やロードマップだけが残り、更新が止まるケースが後を絶ちません。
このギャップの根底には、日本企業に根強い意思決定プロセスの重さがあります。稟議や合意形成に時間を要するため、立ち上げ段階でエネルギーを使い果たし、運用フェーズに入る頃には担当者の余力が残っていない状況が生まれがちです。**計画は完璧でも、実行を支える現実的な体制設計が欠けている**ことが、「机上」で終わる大きな要因です。
さらに、短期的なROIを強く求める経営圧力も影響しています。オウンドメディアは中長期で成果が積み上がる施策ですが、広告のような即効性を期待されると、数か月で「成果が出ない」と判断されやすくなります。その結果、現場は挑戦的な企画を避け、無難な計画だけが積み重なっていきます。
| 認識 | 現場の実態 | 生じる結果 |
|---|---|---|
| 戦略的重要性は高い | 運用リソースが不足 | 計画倒れ |
| 効果を期待 | 短期評価を要求 | 途中撤退 |
| 全社施策のはず | 部門内で完結 | 情報不足 |
また、日本企業ではコンテンツ制作が「特別なクリエイティブ業務」と見なされやすく、業務として標準化されにくい傾向があります。属人的なスキルに依存した結果、担当者の異動や退職で運営が止まる例は珍しくありません。宣伝会議の調査でも、約6割が「コンテンツ数の維持」を最大の課題として挙げており、これは個人ではなく組織の問題だと読み取れます。
加えて、縦割り組織の弊害も無視できません。営業や開発が持つ一次情報が共有されず、表面的な内容の記事しか作れないため、成果につながらないという悪循環に陥ります。**机上メディアとは、能力不足の結果ではなく、組織構造が生み出した必然**だと捉える視点が重要です。
この背景を正しく理解することが、机上の計画を実行に変える第一歩になります。日本企業特有の強みである慎重さや合意形成力は、本来は持続的運用に生かせる資産でもあります。その活かし方を誤ったとき、「机上メディア」という形で表面化しているのです。
データで見るオウンドメディア運営の理想と現実
オウンドメディア運営の理想像として語られるのは、継続的な記事公開による検索流入の増加や、ブランド価値の中長期的な向上です。実際、宣伝会議の調査によれば、回答企業の約8割がオウンドメディアに対してプラスの効果を感じているとしています。多くの企業が価値そのものは強く実感している点は、データ上も明らかです。
一方で、現場の実態に目を向けると、理想とは大きな乖離が存在します。同じ調査において、最大の課題として挙げられたのが「コンテンツ数の維持」で、58.1%もの担当者が悩みとして回答しています。始めることより、続けることの難易度が圧倒的に高いのが、日本のオウンドメディア運営の現実です。
| 項目 | 肯定・課題の割合 |
|---|---|
| オウンドメディアに効果を感じている企業 | 約80% |
| コンテンツ数の維持を課題とする担当者 | 58.1% |
| 制作リソース不足を課題とする担当者 | 48.7% |
この数字が示しているのは、戦略や構想の欠如ではありません。むしろ、Whyは共有されているにもかかわらず、HowとResourceが追いついていない構造的問題です。制作効率の向上を課題に挙げる担当者が約半数に達している点からも、日々の業務の中で記事制作が後回しにされている実情が読み取れます。
さらに定性的なデータを見ると、他部署の協力が得られない、ネタ切れが起きる、退職者の記事管理が滞るといった声が多く報告されています。これらはSEOや編集方針以前の問題であり、運営を支える前提条件が整っていない状態で理想だけが先行していることを示唆しています。
近年は生成AIの活用が進み、すでに34.2%の企業がオウンドメディア運営にAIを取り入れているというデータもあります。ただし、この数字は万能感を示すものではありません。AI導入を検討中の企業が17.9%存在することからも分かる通り、多くの現場では「どう使えば継続できるのか」を模索している段階です。
データで俯瞰すると、日本のオウンドメディア運営は、価値理解の成熟度と実行体制の未成熟さが同時に存在する状態だと言えます。理想が高いからこそ、現実とのギャップが数字として可視化されている点を正しく受け止めることが、次の一手を考える出発点になります。
組織構造が実行を止める理由と属人化のリスク
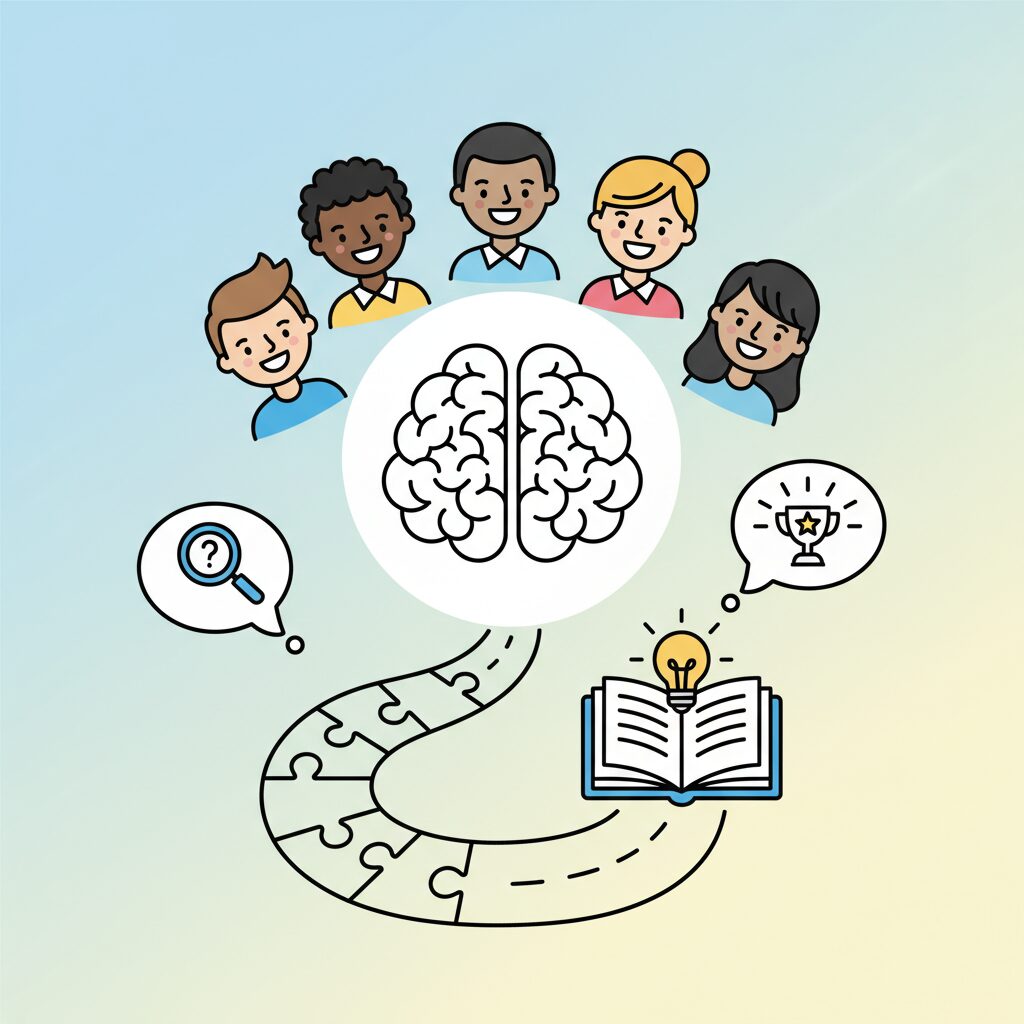
オウンドメディアの実行が止まる背景には、個々の担当者のスキル以前に、組織構造そのものが継続を阻害しているという問題があります。特に多いのが、編集長やエース級ライターなど、特定の個人に業務や判断が集中する属人化の状態です。
この構造では「その人が忙しい」「異動した」「退職した」といった事象が、そのまま更新停止や品質低下に直結します。組織論の分野で言うシングル・ポイント・オブ・フェイラー、つまり一箇所の故障が全体停止を引き起こす状態に陥っているのです。
宣伝会議の調査でも、約6割の担当者がコンテンツ数の維持を最大の課題として挙げていますが、背景にはこの属人化があります。「忙しくて書けない」ではなく、「その人しか書けない構造」こそが本質的なボトルネックです。
| 観点 | 属人化した体制 | 仕組み化された体制 |
|---|---|---|
| 進行 | 特定人物の判断待ちで停滞 | 役割分担により並行進行 |
| 品質 | 個人の力量に依存 | 基準とレビューで安定 |
| 継続性 | 異動・退職で停止 | 担当交代しても継続 |
また、日本企業に多い縦割り組織も実行を鈍らせます。オウンドメディアは営業、開発、カスタマーサポートなどの一次情報が価値の源泉ですが、部署間の壁により協力が得られないケースが少なくありません。その結果、誰でも書けるが誰の責任でもない記事が量産されます。
ハーバード・ビジネス・レビューが指摘するように、知識労働の成果は個人能力よりもプロセス設計に左右されます。にもかかわらず、多くのメディア運営では編集フローや判断基準が暗黙知のまま放置されています。暗黙知が多いほど、属人化と停止リスクは高まります。
さらに問題なのは、立ち上げ期に熱量の高い個人が引っ張った成功体験が、その後の仕組み化を妨げる点です。「あの人がいれば回る」という認識が、体制整備への投資判断を遅らせ、結果的に疲弊と離脱を招きます。
オウンドメディアは短期施策ではなく、年単位で価値を積み上げる事業活動です。だからこそ、人ではなく構造で回る設計が不可欠です。属人化は一時的なスピードを生む一方で、長期的には実行を止める最大のリスクになります。
実行が続かない原因を個人の問題にすり替えず、組織構造の欠陥として捉え直すことが、机上で終わらないメディア運営への重要な転換点となります。
ゴール設計とKPIのズレが現場を疲弊させる
オウンドメディア運営の現場が疲弊する大きな要因の一つが、ゴール設計とKPIのズレです。経営層が描く最終成果と、現場が日々追いかける数値が論理的につながっていないと、担当者は「何のために書いているのか分からない」状態に陥ります。この違和感の蓄積こそが、机上では立派でも実行されないメディアを生み出します。
典型的なのは、「売上に貢献したい」というゴールを掲げながら、KPIとしてPVや記事本数だけが設定されるケースです。PVは分かりやすい指標ですが、それ自体は成果ではなく途中経過にすぎません。マーケティング分野で広く参照されるKPI設計論においても、最終目標から逆算されない指標は行動を誤らせると指摘されています。
このズレが続くと、現場では数字を上げるためだけの記事が量産されます。検索ボリュームの大きいキーワードを優先し、本来届けたい顧客像や検討フェーズを無視したコンテンツが増えていきます。その結果、PVは伸びても商談や採用応募につながらず、経営層からは「やはり成果が出ない」と評価される悪循環が生まれます。
| 設計要素 | ズレた状態 | 現場への影響 |
|---|---|---|
| ゴール | 売上・事業貢献と曖昧に定義 | 判断基準がなく優先順位が迷走 |
| KPI | PV・本数のみを重視 | 質より量の作業感が強まる |
| 評価 | 短期結果のみで判断 | 挑戦や改善が敬遠される |
さらに深刻なのは、評価制度とのねじれです。立ち上げ期で本来は検索エンジンへの認知やコンテンツ蓄積を重視すべき段階でも、即座にCVや売上が求められると、現場は常に失敗前提の目標を課されます。SEOやコンテンツマーケティングは成果までに時間がかかることが、Googleの検索品質評価ガイドラインや多くの専門家の知見からも知られています。
達成不可能なKPIは、努力を成果に変えられないため、担当者の心理的コストを急激に高めます。記事を書いても評価されず、改善しても数字が追いつかない状況では、学習や試行錯誤が止まり、最低限の作業だけをこなす運用に変質していきます。
重要なのは、KPIを管理のための数字ではなく、現場を導く羅針盤として設計することです。ゴールから分解されたKPIであれば、記事一本、順位一つの改善が最終成果にどう寄与するかを説明できます。その説明責任を果たせないKPI設計こそが、静かに現場を疲弊させる最大の原因なのです。
稟議と予算の壁を越えるための経営視点の作り方
オウンドメディアの稟議が通らない最大の理由は、施策そのものではなく、経営視点での語り方が欠けていることにあります。多くの担当者はSEOやコンテンツの有効性を丁寧に説明しますが、経営層が見ているのは検索順位ではなく、事業全体にとっての合理性です。ここで求められるのは、マーケティング施策を経営の意思決定フレームに翻訳する力です。
まず重要なのは、オウンドメディアを「費用」ではなく「資産」として再定義する視点です。宣伝会議の調査によれば、約8割の企業が効果を実感している一方で、予算が十分に確保されていないケースが多いことが示されています。これは、オウンドメディアがPL上の広告費として扱われ、短期回収を前提に評価されているためです。ここで、BS的な資産形成という文脈に置き換えることが、稟議突破の起点になります。
| 視点 | 広告施策 | オウンドメディア |
|---|---|---|
| 会計的扱い | 費用(フロー) | 資産(ストック) |
| 効果の持続性 | 出稿停止でゼロ | 蓄積され継続 |
| CPAの推移 | 基本的に一定 | 長期で逓減 |
次に必要なのが、時間軸を含めた投資ストーリーです。SEOやコンテンツマーケティングは、初期にコストが先行し、後半で回収するJカーブを描きます。バクヤスなどの専門家が指摘するように、初年度の赤字を前提としたシミュレーションをあらかじめ提示することで、「想定外の失敗」という印象を避けられます。いつ、どの指標で成功と判断するのかを明示することが、経営層の不安を下げます。
さらに有効なのが、競合との比較による経営リスクの可視化です。プロスペクト理論で知られる通り、人は利益獲得より損失回避に強く反応します。競合が検索結果上で顧客接点を独占している状況を示すことで、「やらないリスク」を経営課題として提示できます。これはSEOツールによる推計データを用いれば、事実ベースで説明可能です。
最後に、段階的投資という設計も欠かせません。一度に大きな予算を求めるのではなく、検証フェーズ、拡張フェーズ、本格運用フェーズと区切り、各段階で継続判断を行う設計にします。これは経営にとってのオプション価値を高める行為であり、意思決定の心理的ハードルを下げます。オウンドメディアを不可逆な賭けにしないことが、結果として長期的な予算確保につながります。
実行力を高める運用オペレーションの再設計
実行力を高めるためには、戦略やKPI以前に、日々の運用オペレーションそのものを再設計する必要があります。多くのオウンドメディアが失速する原因は、企画や理想像ではなく、日常業務として無理なく回る設計になっていないことにあります。宣伝会議の調査でも、最大の課題として「コンテンツ数の維持」や「制作効率」が挙げられており、これは運用設計の不備を如実に示しています。
まず着手すべきは、業務を人ではなくプロセスで定義することです。企画、構成、執筆、確認、公開、振り返りといった工程を分解し、それぞれに明確な完了条件を設定します。X-BUZZ社の分析によれば、工程が曖昧なまま運用されているメディアほど、更新停止に陥る確率が高いとされています。誰がやるかではなく、どう流れるかを先に決めることが重要です。
このとき有効なのが、プロジェクト管理ツールによる可視化です。Notionなどを用いて各記事の進行状況を一元管理すると、滞留工程が即座に把握でき、属人化も防げます。実際、国内外のコンテンツチームで広く参照されるアトラシアンの調査でも、進行可視化を行うチームは生産性が20%以上向上すると報告されています。
| 工程 | 主な役割 | 完了条件 |
|---|---|---|
| 企画・構成 | 編集・PM | 検索意図と見出し確定 |
| 執筆 | ライター | 初稿提出 |
| 確認・公開 | 編集・運用 | CMS反映と公開 |
次に、生成AIを前提としたオペレーション設計が欠かせません。すでに3割以上の企業が生成AIを活用している現状では、AIを個人の時短ツールとして使うのではなく、工程の一部として組み込む発想が求められます。ベイジの知見でも、企画案や構成案をAIで標準化することで、担当者ごとの品質差を抑えられると示されています。
重要なのは、人とAIの役割分担を明確にすることです。アイデアの発散や要約はAI、一次情報の注入や最終判断は人が担うという線引きを決めておくことで、現場の迷いが減ります。これにより、「AIを使ってよいのか」という心理的ブレーキが外れ、更新頻度の安定につながります。
最後に見落とされがちなのが、運用者体験への投資です。管理画面が重い、入稿が複雑といった小さなストレスは、積み重なると更新意欲を削ぎます。microCMSの導入事例でも、操作性改善によって更新スピードが向上したと報告されています。運用が楽になる設計は、そのまま実行力の強化に直結します。
運用オペレーションの再設計とは、特別な改革ではなく、日々の仕事を続けられる形に整えることです。回る仕組みを先につくることで、オウンドメディアは初めて継続可能な事業活動になります。
生成AIはオウンドメディア運営をどう変えるのか
生成AIの登場は、オウンドメディア運営を単なる効率化の文脈にとどまらず、構造そのものを変えつつあります。これまでの課題は、企画が立派でも実行が続かない点にありましたが、生成AIはこの断絶を埋める現実的な手段として機能し始めています。宣伝会議の調査でも、すでに3社に1社以上がオウンドメディアに生成AIを活用しており、企画や構成といった上流工程への浸透が進んでいます。
特に大きな変化は、コンテンツ制作が「才能や経験に依存する仕事」から「再現可能なプロセス」へと近づいた点です。生成AIを壁打ち相手として活用することで、担当者のコンディションや知識差に左右されにくい企画立案が可能になります。**ネタ切れや属人化が原因で止まっていたメディアが、一定のリズムで更新されるようになる**という変化は、多くの現場で確認されています。
また、生成AIは単なる執筆補助ではなく、意思決定の質にも影響を与えます。過去記事や検索クエリ、社内資料をもとに構成案を生成することで、「なぜこのテーマなのか」「誰に向けた記事なのか」が言語化されやすくなります。これは編集会議や稟議の場での説明コストを下げ、関係者の合意形成を促進します。結果として、企画が承認されずに棚上げされるケースが減少します。
| 工程 | 従来の運営 | 生成AI活用後 |
|---|---|---|
| 企画立案 | 担当者の経験に依存 | AIとの対話で量と質を担保 |
| 構成作成 | 毎回ゼロから作成 | テンプレ化し再利用可能 |
| 継続性 | 人員変動で停止しやすい | プロセスが残り継続しやすい |
一方で、生成AIが万能というわけではありません。ベイジの実務知見でも指摘されている通り、AIが得意なのは発散と整理であり、一次情報の価値判断や文脈に即したニュアンス調整は人の役割です。**生成AIを前提にした運営では、人が何を判断し、どこに責任を持つのかを明確にすることが不可欠**です。この線引きが曖昧なままでは、かえって品質低下や不信感を招きます。
さらに重要なのは、生成AIが「実行されるメディア」を支える基盤になる点です。AIを組み込んだワークフローは、企画から公開までの停滞ポイントを減らし、進行を可視化します。これにより、オウンドメディアは個人の努力に依存した活動から、組織として回る仕組みへと進化します。生成AIはコンテンツを作る道具であると同時に、オウンドメディアを机上の構想から現実の運用へ引き戻す触媒になっているのです。
フェーズごとに考えるKPIマネジメントの最適解
オウンドメディア運営が机上の計画で終わる最大の要因の一つが、KPIを固定値として扱ってしまうことです。メディアは立ち上げから成熟まで明確な成長フェーズを辿りますが、その変化を無視して同じ指標を追い続けると、現場と経営の評価軸が乖離し、実行不全を招きます。
宣伝会議の調査でも、オウンドメディア担当者の多くが「成果が見えない」「評価されにくい」と感じていますが、その背景にはフェーズとKPIの不整合があります。立ち上げ直後にCV数や売上を求められれば、現場は短期施策に偏り、本来必要な土台づくりが疎かになります。
フェーズ別KPIマネジメントの本質は、成功の定義を段階的に切り替える合意形成にあります。Googleも公式に、検索評価には時間がかかると繰り返し言及しており、初期段階での成果は「量と認知」が中心になります。
| フェーズ | 主目的 | 最重要KPI | 評価の視点 |
|---|---|---|---|
| 立ち上げ期 | 存在認知と土台構築 | 記事公開本数・インデックス数 | 計画通り動いているか |
| 成長期 | 検索流入の拡大 | 自然検索流入数・順位 | 再現性が出ているか |
| 成熟期 | 事業貢献 | CV数・CPA | 投資対効果が合うか |
重要なのは、前のフェーズのKPIを捨てないことです。成熟期に入っても記事本数や検索順位のモニタリングを止めてはいけません。KPIは入れ替えるのではなく、重心を移すイメージで管理します。
Webマーケティングメディアferretの事例でも、PV至上主義から脱却し、リードや受注との接続をKPIに組み込むことで、メディアと事業の分断が解消されました。これはKPI変更が組織行動そのものを変えた好例です。
また、KPIは現場がコントロール可能である必要があります。立ち上げ期にPVを追わせるのではなく、「月◯本公開」「制作リードタイム短縮」といった行動KPIを置くことで、実行力が可視化されます。ベイジの生成AI活用ガイドでも、初期は生産量とプロセス指標を重視すべきだと示されています。
フェーズ別KPIマネジメントは、メディアを短距離走ではなくマラソンとして扱うための設計思想です。今どの段階にいるのか、次に何を成功と定義するのかを言語化できた瞬間、オウンドメディアは机上の企画から、動き続ける組織資産へと変わります。
先進企業の事例に学ぶオウンドメディア成功のヒント
先進企業のオウンドメディアに共通しているのは、華やかな成功要因よりも、一度は直面した「行き詰まり」をどう乗り越えたかにあります。計画倒れに終わらず、実行され続けるメディアには、組織や事業と深く結びついた設計思想が存在します。
代表的な事例が、サイボウズの「サイボウズ式」です。同メディアは製品紹介やSEO流入を主目的とせず、「チームワークあふれる社会をつくる」という企業理念そのものを編集方針の中核に据えています。ハフポスト日本版などでも紹介されている通り、同社はかつて高い離職率に悩み、組織改革の過程で多くの試行錯誤と失敗を経験しました。そのプロセスを隠さずコンテンツ化した点が、読者の強い共感を生み、結果として採用やブランド好意度の向上につながっています。
重要なのは、完成された成功談ではなく、進行形の課題や葛藤を発信している点です。これにより「ネタ切れ」という多くのメディアが抱える問題を、構造的に回避しています。自社の組織課題や意思決定の背景そのものが一次情報となり、他社が模倣できない独自性を獲得しているのです。
| 観点 | サイボウズ式の特徴 |
|---|---|
| テーマ設計 | 製品ではなく企業理念と組織変革 |
| 情報源 | 社内の実体験・失敗・議論 |
| 成果 | 採用ブランディングと高いエンゲージメント |
もう一つ示唆に富むのがLIGブログです。かつてはバズを生む面白記事で知られていましたが、事業がWeb制作からDX支援へと変化する中で、メディアの役割も大胆に転換しました。Wantedlyで公開されている同社のストーリーによれば、過去の成功体験に固執せず、「今の事業にとって意味のある読者は誰か」を再定義したことが転機となっています。
この事例から学べるのは、オウンドメディアを固定的な成果物として扱わない姿勢です。事業戦略が変われば、メディアのKPIやトーン、扱うテーマが変わるのは自然なことです。長く続いているメディアほど、節目ごとにピボットを行い、自らの役割を更新しています。
先進企業の事例が示しているのは、成功の近道となるテクニックではありません。オウンドメディアを「別プロジェクト」にせず、事業・組織・文化の延長線上に置くことこそが、実行不全に陥らない最大のヒントだと言えます。
参考文献
- PR TIMES:8割「オウンドメディアの効果」を実感するも…
- 検索順位の海賊:オウンドメディアが継続できない理由|戦略があれど実行されないと意味ない!
- X-BUZZ:オウンドメディアが継続できない?失敗の原因と有効な対策を紹介
- FastGrow:ferretで劇的に成果を上げた、オウンドメディア経由のリードを成約へ導いた裏側
- BAKUYASU:SEO社内稟議を通す5つのコツ|承認率を上げる書き方・説得術
- ベイジの図書館:オウンドメディアのための生成AI活用ガイド
- microCMS:導入事例インタビュー【株式会社ALBA様】コンテンツ更新の速報性を支える仕組み