生成AIの普及により、オウンドメディアを取り巻く環境は大きく変化しました。誰でも一定品質の記事を量産できる一方で、「どの記事も同じに見える」「検索順位が伸びない」と悩む運用者は少なくありません。情報が溢れる今だからこそ、オウンドメディアの価値そのものが問われています。
その中で注目されているのが、営業現場に眠る一次情報や暗黙知です。顧客の生の声、導入時のリアルな課題、失敗や成功の背景といった情報は、生成AIでは再現できない強力な差別化要素になります。Googleが重視するE-E-A-T、とりわけ「経験(Experience)」を満たすうえでも、営業の知見は欠かせません。
しかし現実には、「営業が忙しくて取材できない」「連携したいが仕組みがない」という壁に多くの企業が直面しています。本記事では、営業担当者の時間を奪わずに暗黙知を抽出し、SEOとAIOの両面で評価されるオウンドメディアへ昇華させるための考え方と戦略を整理します。営業とマーケティングが分断されたままの状態から一歩踏み出したい方にとって、実践のヒントが得られる内容です。
生成AI時代にオウンドメディアが直面する本当の危機とは
生成AIの普及によって、オウンドメディアはかつてない危機に直面しています。その本質は「記事が作れなくなること」ではありません。**誰でも一定水準の記事を量産できるようになった結果、コンテンツそのものの価値が急激に下落していること**にあります。
HubSpot Japanの調査によれば、2024年時点でマーケターの81.6%が生成AIを業務に活用しています。これは生成AIが一部の先進企業の武器ではなく、すでに業界標準のインフラになったことを意味します。その結果、SEOを意識した網羅的で読みやすい記事は、もはや差別化要因になりません。
この変化は検索エンジン側にも影響を与えています。Googleが重視するE-E-A-Tの中でも、特にExperience、つまり「実体験に基づく情報」が評価の中心に据えられるようになりました。**AIが生成できるのは過去データの平均解であり、現場で起きた具体的な経験そのものではない**からです。
| 項目 | 生成AI以前 | 生成AI以後 |
|---|---|---|
| 記事作成コスト | 高い | 極めて低い |
| 差別化要因 | 文章力・情報量 | 一次情報・経験 |
| 評価される価値 | 網羅性 | 信頼性と独自性 |
ここで多くのオウンドメディアが陥るのが、「AIを使って記事数を増やす」という誤った最適化です。情報がコモディティ化した環境では、量を増やすほど他サイトとの差が縮まり、結果として検索エンジンからもユーザーからも選ばれにくくなります。
さらに深刻なのは、ユーザー側の変化です。BtoB領域では、意思決定者の多くが営業と接触する前に情報収集を終えています。この段階で求められているのは一般論ではなく、「自分と同じ立場の企業が、どんな失敗をし、どう乗り越えたのか」という具体的な文脈です。**平均点の正しい情報は、意思決定を前に進めない**のです。
つまり、生成AI時代における本当の危機とは、検索順位の低下やPV減少そのものではありません。**自社のオウンドメディアが、意思決定に影響を与えられない“無難な情報置き場”に成り下がること**です。この危機を正しく認識できない限り、どれだけAIを使いこなしても、成果にはつながりません。
情報のコモディティ化とE-E-A-Tが重視される理由
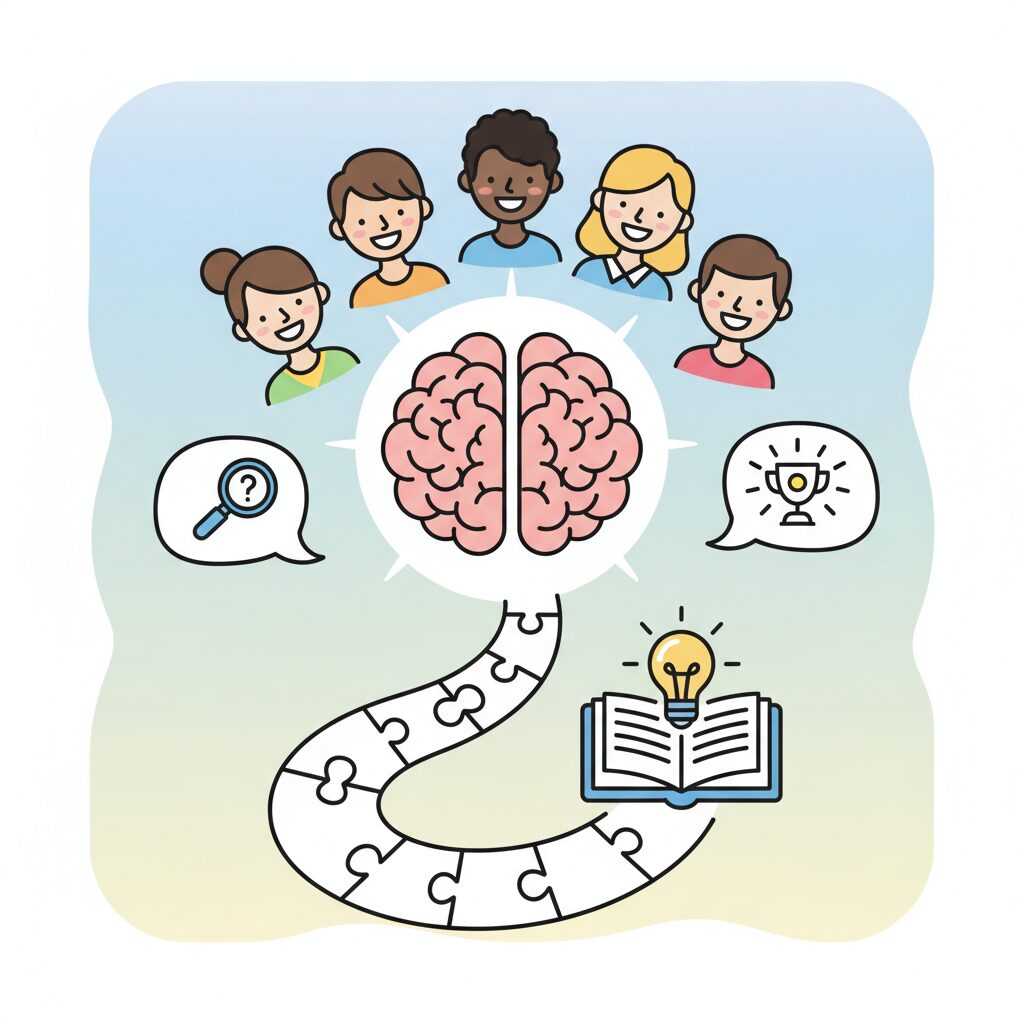
生成AIの普及によって、情報の価値構造は大きく変わりました。文章生成や要約、調査整理といった行為は、もはや特別なスキルではなくなり、誰でも短時間で一定水準のコンテンツを作れる時代に突入しています。HubSpot Japanの調査でも、国内マーケターの8割以上が生成AIを業務に活用していると報告されており、情報発信のハードルは劇的に下がっています。
その結果として起きているのが、情報のコモディティ化です。検索結果には似た構成、似た結論、似た表現の記事が並び、ユーザーにとっては「どれを読んでも同じ」に見える状態が常態化しています。**情報量の多さが価値になるフェーズは終わり、情報の背景や出どころが問われるフェーズに移行している**と言えます。
この環境変化に対応するため、検索エンジン側も評価軸を進化させています。Googleの検索品質評価ガイドラインで重視されるE-E-A-Tは、その象徴です。特に近年追加されたExperienceは、実体験に基づく一次情報かどうかを厳しく見極める考え方であり、生成AIが大量生産する平均的なコンテンツとの差別化ポイントになっています。
| 評価観点 | コモディティ化した情報 | E-E-A-Tを満たす情報 |
|---|---|---|
| 情報源 | 二次・三次情報の再編集 | 現場や当事者の一次情報 |
| 再現性 | 誰でも生成可能 | 特定の人・組織のみ可能 |
| 信頼シグナル | 薄い | 強い |
専門家の間でも、この流れは明確に指摘されています。SEOの研究や実務分析を行う複数の企業が、E-E-A-Tの強化要素として「誰が、どの立場で、どんな経験をもとに書いているか」を明示する重要性を挙げています。単に正しいことが書かれているだけでは不十分で、「その人が語る必然性」がなければ評価されにくくなっています。
また、ユーザー側の行動変化も無視できません。BtoB領域では、購買検討の大半が営業接触前にオンラインで行われると言われています。この段階で読まれるのは、表面的な解説記事ではなく、**自分と同じ立場の企業が実際に悩み、失敗し、どう乗り越えたのかが具体的に描かれた情報**です。ここに経験価値の需要が集中しています。
情報が溢れるほど、検索エンジンもユーザーも「信じられるかどうか」を重視します。E-E-A-Tが重要視される理由は、アルゴリズムの気まぐれではなく、情報のコモディティ化という構造的な問題への必然的な回答です。オウンドメディアが選ばれ続けるためには、この前提を正しく理解することが不可欠です。
一次情報の宝庫である営業現場が注目される背景
生成AIの普及によってコンテンツ制作の効率は飛躍的に高まりましたが、その一方で、オウンドメディア運用者の間では「何を書いても差別化できない」という閉塞感が広がっています。HubSpot Japanの調査によれば、すでに8割以上のマーケターが生成AIを業務に活用しており、文章のうまさや情報量そのものは競争優位になりにくくなっています。だからこそ今、**誰もが持っていない一次情報の源泉として営業現場が強く注目されている**のです。
営業現場には、検索結果や業界レポートには決して表れない「生の経験」が日々蓄積されています。顧客が検討段階で口にする率直な不安、競合製品と比較した際の本音の評価、社内稟議でつまずいた具体的な理由などは、営業担当者と顧客の対話の中でしか生まれません。Googleが品質評価で重視するE-E-A-Tの中でも、特にExperienceの要素は、こうした現場由来の情報によってのみ担保されるとされています。
この流れを後押ししているのが、BtoB購買行動の変化です。近年の研究や調査では、BtoBバイヤーは営業と接触する前に意思決定プロセスの大半をオンラインで進めていると指摘されています。その段階で求められているのは、抽象的な機能説明ではなく、**自分たちと似た立場の企業が実際に直面した課題と、その乗り越え方**です。営業現場の一次情報は、このニーズと極めて高い親和性を持っています。
| 情報の種類 | 主な発生源 | 検索ユーザーへの価値 |
|---|---|---|
| 一般的な知識 | 公開資料・AI生成 | 理解の補助 |
| 統計・データ | 公的機関・調査会社 | 判断材料 |
| 一次情報 | 営業現場 | 意思決定の後押し |
さらに、営業現場が注目される理由として、情報の希少性と再現性の低さがあります。AIは過去データをもとに平均解を提示することは得意ですが、「昨日の商談で顧客が一瞬言い淀んだ理由」や「失注後に明かされた本当の懸念」といった文脈依存の情報は生成できません。こうした情報は他社が容易に模倣できず、結果としてオウンドメディア全体の信頼性と被引用性を高めます。
実際、SEOやコンテンツマーケティングの専門家の間でも、現場情報を含むコンテンツは被リンクや指名検索につながりやすいと指摘されています。一次情報を含む記事は「引用される側」になりやすく、ドメイン全体の評価向上にも寄与します。**営業現場は単なるネタ提供先ではなく、メディア価値を底上げする戦略的資産**として再評価され始めているのです。
このように、情報のコモディティ化、検索アルゴリズムの進化、そして購買行動の変化が重なった結果、営業現場は今、かつてないほど注目を集めています。オウンドメディアにおいて成果を出すためには、この現場に眠る一次情報の価値を正しく理解することが、すべての出発点になりつつあります。
なぜ営業とオウンドメディアは連携できないのか
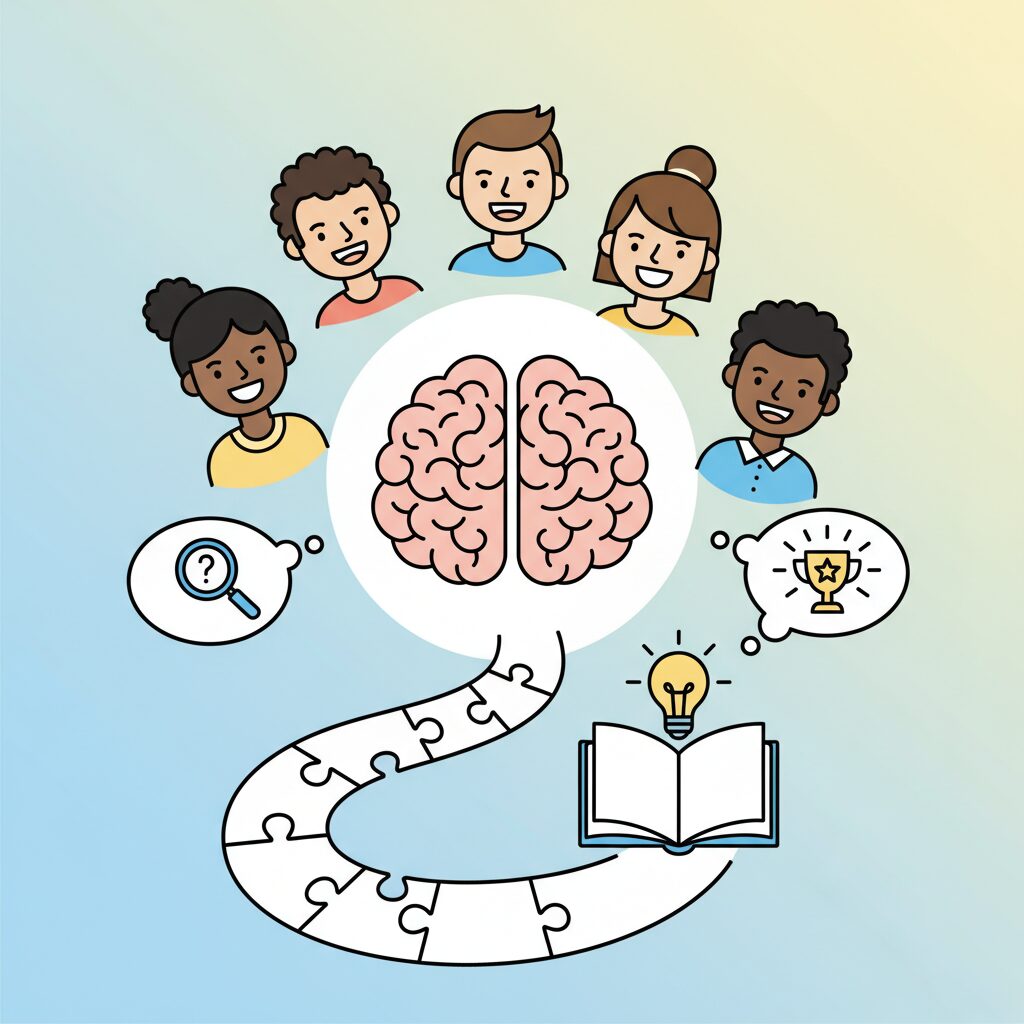
営業とオウンドメディアが連携できない最大の理由は、個人の協力度や意識の低さではなく、役割と成果の定義が構造的に分断されている点にあります。多くの企業で営業は売上を、オウンドメディアはPVやリード数を追っていますが、この指標の違いが「協力すると自分の仕事が増えるだけ」という認識を生み出しています。
HubSpot Japanの調査によれば、生成AIの普及によりマーケティング業務の効率は向上した一方で、部門間連携を強化するための業務設計を見直している企業は全体の4分の1程度にとどまっています。つまり、多くの組織ではテクノロジーだけが先行し、営業とメディアをつなぐ評価軸や業務フローが更新されていないのが実情です。
営業側の視点に立つと、オウンドメディアへの協力は「売上に直結しない割り込みタスク」に見えやすいです。Sales Marker社の調査でも、アウトバウンド営業を行う企業の多くが商談率や受注率に課題を感じているとされており、数字へのプレッシャーが強い環境下では、取材対応や情報提供の優先順位が下がるのは合理的な判断と言えます。
一方で、オウンドメディア側は「一次情報が重要だ」と理解していながら、営業の暗黙知をどう引き出せばよいか分からず、結果として一般論や二次情報に依存した記事を量産してしまいがちです。このすれ違いが続くと、営業からは「協力しても役に立たない記事になる」、メディア側からは「営業は非協力的だ」という相互不信が蓄積されます。
| 観点 | 営業部門の認識 | オウンドメディア側の認識 |
|---|---|---|
| 成果指標 | 受注・売上・商談数 | PV・検索順位・リード数 |
| 情報の価値 | 個人の経験知・ノウハウ | 再現可能なコンテンツ素材 |
| 協力の意味 | 自分の時間を削る行為 | メディア品質向上のために不可欠 |
さらに問題を深刻化させているのが、日本企業に根強い組織のサイロ化です。WACUL代表の垣内勇威氏が指摘するように、業務プロセスごとに部署を細かく分けすぎた結果、情報が部門内で閉じてしまい、顧客の声が組織横断で共有されない構造が生まれています。この状態では、営業の現場で得られた貴重な経験がメディアに届く前に消失してしまいます。
加えて、過去の失敗体験も連携を阻害します。取材に協力したものの、記事がいつ公開されたのか分からない、商談で使える形になっていない、成果のフィードバックがない。このような経験を一度でもすると、営業担当者は「もう関わらない方が得だ」と学習してしまいます。これは個人の怠慢ではなく、貢献が可視化されない設計ミスの問題です。
本質的に、営業とオウンドメディアは同じ顧客理解を目指しているにもかかわらず、その接続点が設計されていません。連携できないのは意志の問題ではなく、成果指標、業務優先度、情報の流れが噛み合っていないからです。この構造を理解せずに「もっと協力してほしい」と求め続けても、状況が改善することはありません。
営業担当者の負担を増やさない暗黙知抽出の考え方
営業担当者の負担を増やさずに暗黙知を引き出すためには、まず「知識を話してもらう」という発想自体を捨てる必要があります。営業の暗黙知は、本人が整理して語れる状態では存在していません。**行動や反応、瞬間的な判断の中に溶け込んでいるため、長時間の取材や事前準備を求めるほど抽出は難しくなります。**
この前提に立つと、有効なのは「営業の業務フローを一切変えない」設計です。たとえば商談後に詳しい振り返りを依頼するのではなく、商談直後の一言や短い選択理由を拾います。行動経済学でいうピーク・エンドの法則が示す通り、人は出来事の最中よりも、直後の印象に最も本音が残ります。ここにこそ、顧客理解や勝ち筋の暗黙知が凝縮されています。
ハーバード・ビジネス・スクールの研究でも、熟練者の判断は言語化された理屈よりも「状況に対する即時反応」に現れるとされています。営業担当者が「なぜその提案をしたのか」を説明できなくても、「その瞬間に何を選ばなかったか」を聞くことで、意思決定の軸が浮かび上がります。**重要なのは説明力ではなく、選択の痕跡を集めることです。**
| 抽出の視点 | 営業の負担 | 得られる一次情報 |
|---|---|---|
| 事後インタビュー | 高い | 整理された建前 |
| 商談直後の一問 | 極小 | 判断基準・感情 |
また、暗黙知抽出を「協力依頼」にすると、営業は無意識に防御姿勢を取ります。一方で「記録」「観察」「ついで」の形にすれば、心理的コストはほぼゼロになります。オンライン商談のログやSFAの自由記述欄が有効なのは、営業がアウトプットを意識していない状態で残された情報だからです。**無意識下の言葉ほど、コンテンツとしての独自性が高まります。**
GoogleのE-E-A-Tで重視されるExperienceは、丁寧に説明された成功談よりも、判断に迷った瞬間や想定外の反応に宿ります。営業担当者の時間を奪わず、その一瞬を切り取る。この設計思想こそが、暗黙知を資産化する上での核心です。
商談ログ・SFAデータを活用した一次情報の活用戦略
商談ログやSFAデータは、営業活動を管理するための裏方データとして扱われがちですが、実は一次情報の宝庫です。特に生成AI時代においては、このような現場由来のデータこそが、E-E-A-Tの中核である「Experience」を裏付ける希少な情報源になります。
HubSpot Japanの調査によれば、日本のマーケターの8割以上が生成AIを業務に活用しています。一方で、誰もが似たような記事を作れる環境になったことで、検索エンジンは「どこで得られた情報か」「実際の現場で使われている知見か」をこれまで以上に重視するようになっています。
この要請に最も自然に応えられるのが、営業現場に日々蓄積されている商談ログとSFAデータです。
商談ログが生む「顧客インテントの生データ」
オンライン商談の録画・文字起こしデータには、顧客が本音で語った質問や懸念、反論がそのまま残っています。これはアンケートや机上調査では取得できない、極めて純度の高い一次情報です。
例えば、商談解析ツールを用いてログを分析すると、以下のような情報が抽出できます。
| 抽出要素 | コンテンツ化の切り口 |
|---|---|
| 頻出する質問 | FAQ記事、誤解を解く解説記事 |
| 導入を迷う理由 | 比較・検討フェーズ向けの記事 |
| 強い反論や不安 | 失敗回避・注意点を伝える記事 |
Googleの検索品質評価ガイドラインが示すように、「実際にその状況を経験した人しか書けない内容」はアルゴリズム上も高く評価されます。商談ログは、その経験を後からでも再利用できる形で保存している点が最大の強みです。
SFAデータは「なぜ売れたか・なぜ売れなかったか」の集合知
SFAやCRMに入力されているデータの中で、特に注目すべきなのは失注理由、競合情報、営業メモといったテキスト情報です。これらは数字だけでは見えない文脈を含んでいます。
例えば「価格が高い」という失注理由が多い場合、それは単なる値付けの問題ではなく、価値の伝達やターゲット設定に課題がある可能性を示唆しています。この気づきを記事として言語化することで、同じ誤解を持つ読者に先回りして答えることができます。
失注データをコンテンツに変換することは、営業とマーケティング双方の生産性を高める行為です。営業は説明コストを下げられ、マーケティングは成約に近い検索意図を捉えられます。
営業の手を止めない設計が成功の分かれ目
Sales Markerの調査でも示されている通り、多くの営業組織は常に商談率・受注率のプレッシャーにさらされています。その中で重要なのは、営業に「協力してもらう」発想ではなく、既に存在するデータを二次利用する設計です。
商談を録画する、SFAの入力項目を標準化する、といった小さなルール整備だけで、マーケティング側は継続的に一次情報を取得できます。オウンドメディアがこの仕組みを持つことで、外部情報に依存しない、再現性のあるコンテンツ供給体制が完成します。
商談ログとSFAデータを活用した一次情報戦略は、単なる効率化ではありません。それは営業現場の知見を企業の知的資産へと昇華させるプロセスであり、生成AI時代におけるオウンドメディアの競争優位を根本から支える基盤となります。
E-E-A-Tを高めるための営業知見コンテンツ化のポイント
営業知見をコンテンツ化する際にE-E-A-Tを高める最大のポイントは、単なる情報提供ではなく、「誰の、どの経験から生まれた知見なのか」を明確に構造化することです。生成AI時代においては、内容の網羅性や文章の整合性だけでは差別化できず、検索エンジンも読者も「その話は本当に現場から出てきたのか」を厳しく見ています。
Googleの検索品質評価ガイドラインが示すExperienceは、一次体験に基づく具体性を重視します。営業コンテンツにおいては、抽象化しすぎた成功論よりも、顧客の発言や意思決定の揺らぎ、導入直前で発生した想定外の障壁といったディテールが評価を押し上げます。HubSpot Japanの調査でも、生成AI活用が進む一方で、成果につながるコンテンツの条件として「実体験の反映」を挙げるマーケターが増えていることが示されています。
このとき重要なのが、営業担当者個人の武勇伝に終わらせない編集設計です。経験談をそのまま書き起こすのではなく、専門家としての解釈を重ねることでExpertiseが生まれ、企業として継続的に再現可能な知見へと昇華されます。たとえば「価格が高いと言われた商談」の裏側には、購買プロセスや意思決定構造に関する汎用的な示唆が含まれています。
| 営業現場の情報 | 編集視点 | E-E-A-Tへの寄与 |
|---|---|---|
| 顧客からの反論や懸念 | 背景要因と判断軸の解説 | Experience / Expertise |
| 失注理由の具体例 | 再発防止のための構造化 | Trustworthiness |
| 想定外の活用事例 | 汎用化できる成功条件の抽出 | Authority |
さらにE-E-A-Tを強化するうえで欠かせないのが、営業知見の出所と検証可能性を示すことです。匿名化を前提に「複数の商談ログを分析した結果」「直近◯件の受注データから見えた傾向」といった表現を用いることで、個人の感想ではなく組織的知見としての信頼性が高まります。これはSEOだけでなく、営業資料として二次利用される際の説得力にも直結します。
米国のBtoBコンテンツ研究でも、一次情報を含む記事は被リンク獲得率が高く、結果としてドメイン全体の評価を押し上げる傾向があると報告されています。営業現場の知見は、まさにこの一次情報の宝庫であり、正しく編集すれば企業の権威性を裏付ける「引用される情報源」になり得ます。
最後に、営業知見コンテンツ化を継続させるためには、営業担当者自身が価値を実感できる形で還元することが不可欠です。自分の経験が記事となり、商談で使われ、実際の受注につながる。その循環が可視化されたとき、営業は単なる協力者ではなく、信頼性を共創する当事者になります。この関係性こそが、E-E-A-Tを中長期で高め続ける最も強固な基盤となります。
生成AIを編集者として活用するコンテンツ制作プロセス
生成AIをコンテンツ制作に活用する際、最も価値を発揮する役割は「執筆者」ではなく「編集者」ですます。AIにすべてを書かせる運用は効率的に見えますが、情報の独自性や信頼性という観点では限界があります。HubSpot Japanの調査でも、多くのマーケターが生成AIを使いながらも、成果に直結する活用には試行錯誤していることが示されています。そこで重要になるのが、AIを編集工程に組み込み、人間の一次情報を磨き上げるプロセス設計ですます。
具体的には、営業日報や商談ログ、Slack上の現場コメントといった素材を人間が集め、その整理と構造化をAIに任せます。AIは情報の抜け漏れチェック、論点の整理、読者視点での再構成に優れており、編集者として機能させることで人間の経験価値を最大化できます。Googleの検索品質評価ガイドラインが重視するExperienceの観点でも、一次情報を起点にAIが編集補助に回る形は極めて合理的ですます。
特に効果が高いのは、AIに「何を書くか」ではなく「どう磨くか」を指示するプロンプト設計ですます。例えば、単なる要約ではなく「顧客の誤解はどこか」「意思決定を阻んでいる不安は何か」といった編集者視点の問いを与えることで、記事の解像度が一段上がります。これはBtoBマーケティングの現場で推奨されているHuman-in-the-loopの考え方とも一致します。
| 工程 | 人間の役割 | 生成AIの役割 |
|---|---|---|
| 素材収集 | 営業現場の一次情報を確保 | 関与しない |
| 構造整理 | 論点の妥当性を判断 | 情報の分類・不足指摘 |
| 編集・推敲 | 経験や文脈を追記 | 表現改善・構成提案 |
このプロセスを取ることで、編集スピードと品質を同時に引き上げることができますます。WACULが提唱するテンプレート活用の思想とも親和性が高く、AIに定型構成への当てはめを任せることで、編集者は独自視点の確認に集中できます。結果として、属人性に依存しない再現性の高い制作体制が構築されます。
また、AIを編集者として使うことで、社内レビューの質も向上しますます。AIに想定読者や検索インテントを与え、「読者が次に知りたくなる点は何か」「説明が足りない箇所はどこか」を指摘させることで、第三者視点の校正が可能になります。これは経験豊富な編集者が常に横にいる状態を疑似的に再現するものですます。
生成AIは万能な自動化装置ではなく、編集判断を支援する知的補助輪ですます。人間が一次情報と最終責任を担い、AIが編集工程を支える。この役割分担を明確にしたとき、オウンドメディアは量産型コンテンツから脱却し、信頼される情報資産へと進化していきますます。
営業を巻き込むための組織設計とインセンティブの考え方
営業をオウンドメディアに巻き込むために最も重要なのは、個々人の善意や協力姿勢に期待しない組織設計です。営業担当者は売上という明確な責任を背負っており、そこに直結しない活動は後回しにされるのが合理的です。したがって必要なのは、オウンドメディアへの関与が結果的に営業成果を高めると、構造として理解できる状態を作ることです。
まず設計すべきは役割分担です。営業に「記事ネタを考えてもらう」「原稿を確認してもらう」といった作業を求めると、負担感が一気に高まります。営業の役割はあくまで一次情報の供給者に限定し、編集・加工・公開の責任はマーケティング側が一手に引き受けます。**営業は話すだけ、マーケは形にするだけ**という非対称な分業が、継続性を担保します。
| 設計観点 | 営業側の負担 | マーケ側の責任 |
|---|---|---|
| 情報提供 | 商談・失注理由をそのまま共有 | 文脈整理・匿名化・編集 |
| 成果管理 | 直接的な数値責任なし | 流入・商談貢献の可視化 |
| 改善 | 一言コメントのみ | 記事改善・再活用 |
次に重要なのがインセンティブ設計です。金銭報酬を即座に用意できない場合でも、行動経済学的に有効な手段は存在します。HubSpot Japanの調査でも示されている通り、人は自分の行動が成果に結びついていると実感できたときに、継続的に関与しやすくなります。そこで有効なのが、貢献の可視化と承認です。
具体的には、記事経由で発生したリードや商談をSFA上でひも付けし、営業本人にフィードバックします。Googleが重視するE-E-A-Tの観点でも、現場起点の記事は評価されやすく、結果として指名検索や比較検討フェーズでの接触機会が増えます。営業にとっては、説明コストの削減や商談の前倒しという形でリターンが返ってきます。
さらに一歩進めるなら、評価制度との接続です。WACUL代表の垣内勇威氏が指摘するように、部門間連携はトップマネジメントの意思がなければ定着しません。オウンドメディアへの協力を「全社売上への間接貢献」と位置づけ、表彰や定性評価の項目に組み込むだけでも、営業の認識は大きく変わります。
営業を巻き込むとは、お願いすることではなく、合理的に参加したくなる構造を作ることです。組織設計とインセンティブが噛み合ったとき、オウンドメディアはマーケティング施策ではなく、営業活動の延長線として機能し始めます。
参考文献
- マナミナ(HubSpot Japan調査):日本のマーケティングに関する意識・実態調査の結果を発表
- Sales Marker:【BtoB営業の実態調査】アウトバウンド営業を実践する企業の89%が事業成長を実感
- B2Bデジマ備忘録:生成AI時代のSEO対策|E-E-A-Tの高め方
- BtoBマーケティングの教科書:SEO記事制作におけるE-E-A-Tを担保する方法
- N-works:WACUL代表・垣内勇威が考えるデジタルマーケティングと組織連携
- ITreview:オンライン商談ツールのおすすめ比較
