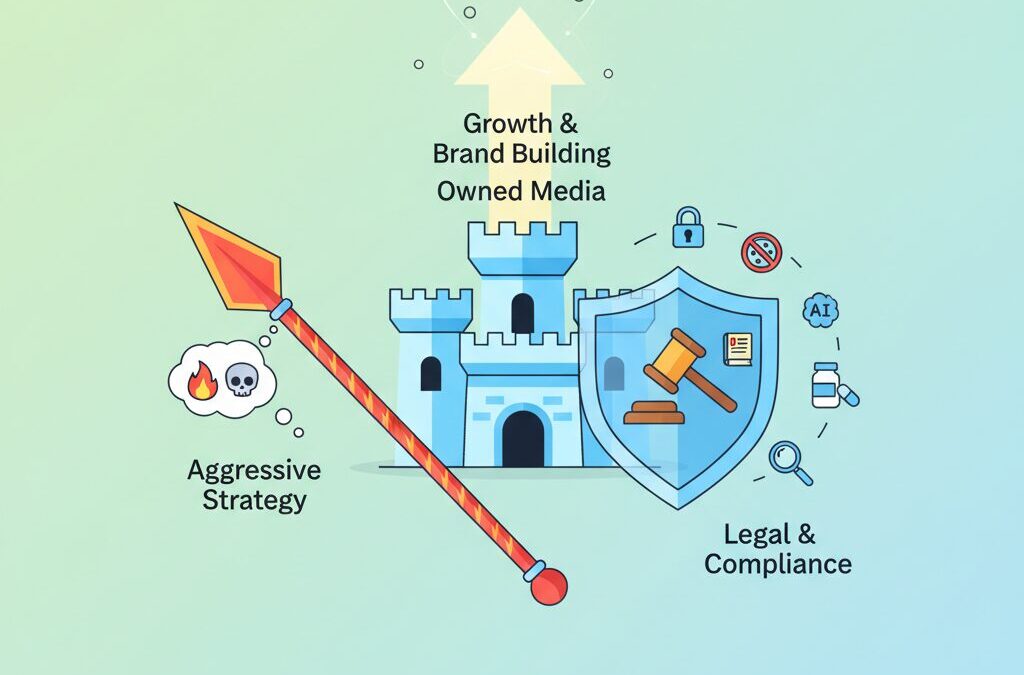オウンドメディアを運用していると、「もっと踏み込んだ記事を書きたいのに、法務チェックが厳しくて通らない」「炎上や違反が怖くて、無難な内容ばかりになってしまう」と感じたことはないでしょうか。
2024年から2025年にかけて、ステルスマーケティング規制の本格運用、薬機法の摘発強化、生成AIと著作権の問題、そしてサードパーティCookie規制など、メディア運営を取り巻く環境は一段と厳しくなっています。その一方で、ファーストパーティデータ活用やブランド構築の観点から、オウンドメディアへの期待はこれまで以上に高まっています。
つまり今、オウンドメディアには「攻めなければ成果が出ない」というマーケティングの要請と、「一歩間違えれば信頼を失う」という法的リスクが同時に突きつけられています。本記事では、この二律背反を乗り越えるために、最新の法規制動向や実際の事例を踏まえながら、攻めと守りを両立させるための考え方と全体像を整理します。読み終えたとき、自社メディア運用の次の一手が明確になるはずです。
なぜ今、オウンドメディア運用はこれほど難しくなっているのか
オウンドメディア運用が難しくなっている最大の理由は、集客構造の激変と法規制強化が同時進行している点にあります。2024年後半からGoogle ChromeでサードパーティCookieの段階的廃止が本格化し、従来の広告依存型集客は急速に効果を失いました。
その結果、企業は自社で読者との接点を持ち、同意を得た上でデータを蓄積するファーストパーティデータ戦略へと舵を切らざるを得なくなっています。読者が自ら情報を提供したいと思うほどの価値あるコンテンツが不可欠になり、オウンドメディアの重要性はかつてなく高まっています。
一方で、発信内容に対する社会の目は極端に厳しくなりました。消費者庁によるステルスマーケティング規制は2024年に初の措置命令事例を生み、広告と分かりにくい表現が実際に違法と判断されています。
さらに薬機法違反では、2024年に未承認医薬品広告を巡る逮捕事例が発生しました。コンテンツの一文が刑事リスクに直結する時代に突入したと言えます。
| 環境変化 | 運営への影響 | 現場の課題 |
|---|---|---|
| Cookie規制 | 広告集客の弱体化 | 自力で読者を集める必要 |
| ステマ規制 | 広告表現の明確化義務 | PRと編集の線引き |
| 薬機法強化 | 表現違反の刑事化 | 専門知識不足のリスク |
この状況下で多くの企業が陥っているのが、過剰なリスク回避です。法務チェックへの恐怖や炎上不安から、無難で誰の心にも刺さらない表現に収束してしまいます。
Voicyが公表した調査では、ハラスメントを恐れて指導を控える「ハラ萎縮」を経験した人が約8割に上るとされています。この心理的萎縮はメディア運用にもそのまま表れ、挑戦的な企画や独自視点が封じられているのが実情です。
結果として、法的には安全でも差別化できないコンテンツが量産され、読まれないオウンドメディアが増えています。難しさの本質は、単なるSEOや制作スキル不足ではなく、攻める必要性と守る必要性が同時に高まった構造的ジレンマにあるのです。
ポストCookie時代にオウンドメディアが担う役割の変化
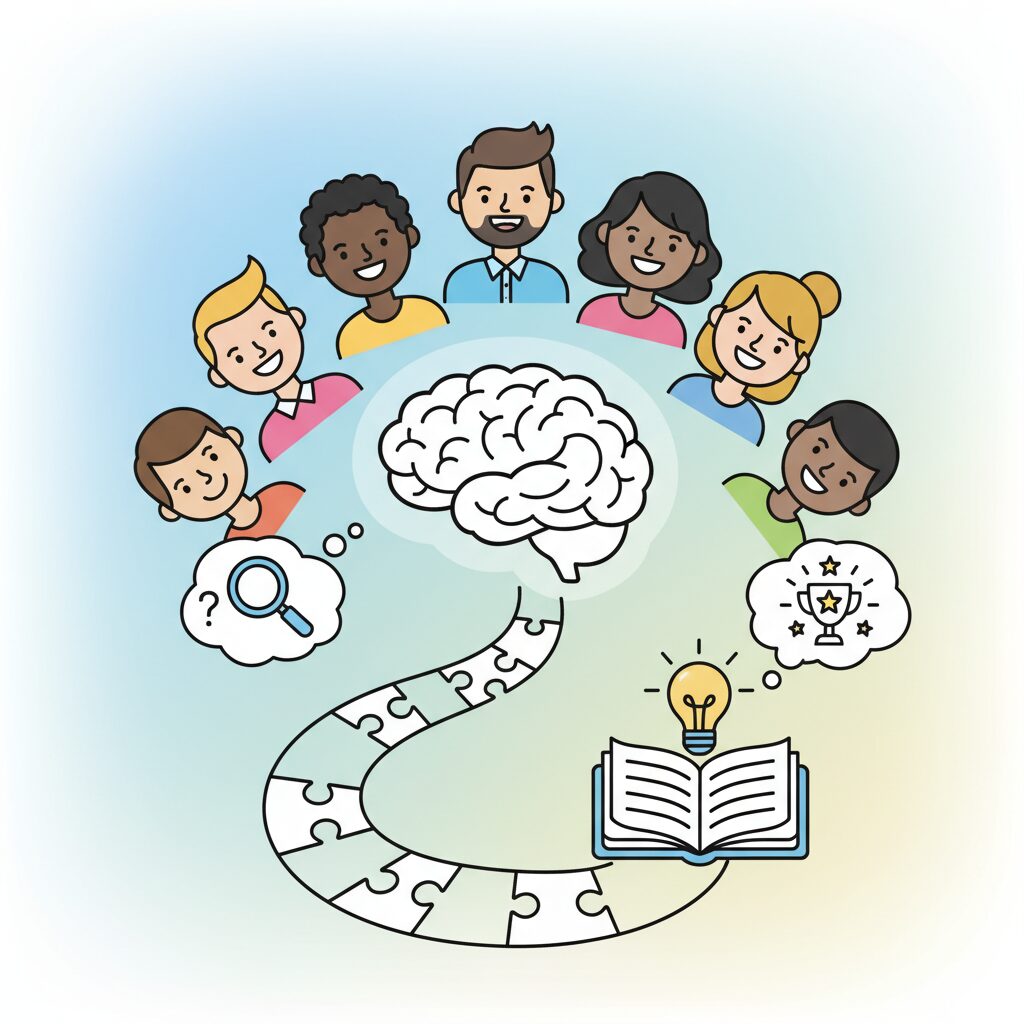
ポストCookie時代において、オウンドメディアの役割は「集客装置」から「信頼を基盤としたデータ取得・活用の中核」へと大きく変化しています。Google ChromeによるサードパーティCookieの段階的廃止が進み、従来主流だった行動追跡型広告や精緻なリターゲティングは機能不全に陥りつつあります。
この環境変化は、広告効率の低下という短期的な課題にとどまらず、企業と顧客の関係性そのものを問い直す契機となっています。外部プラットフォームに依存して断片的な接点を持つのではなく、企業自らが価値ある情報を提供し、読者の明確な同意のもとでファーストパーティデータを蓄積する拠点として、オウンドメディアが再定義されているのです。
| 観点 | Cookie依存時代 | ポストCookie時代 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 広告流入の受け皿 | 信頼と同意を生む接点 |
| 重視される価値 | PV・CTR | エンゲージメント・継続接触 |
| データの性質 | 外部取得・匿名中心 | 自社取得・同意ベース |
重要なのは、ファーストパーティデータが単なる代替手段ではない点です。氏名やメールアドレスといった情報は、読者が「このメディアなら信頼できる」と判断した結果として提供されます。つまりオウンドメディアは、データ取得の前提条件となる信頼を設計・蓄積するメディアでなければ成立しません。
消費者庁や総務省が示す個人情報・外部送信規律の考え方によれば、データ活用には透明性と説明責任が不可欠とされています。Cookie同意バナーやプライバシーポリシーは単なる法対応ではなく、企業姿勢を可視化するタッチポイントです。ここで不誠実な印象を与えれば、登録や継続購読といった行動は期待できません。
また、ポストCookie時代のオウンドメディアは、短期的な刈り取りよりも中長期の関係構築が評価軸になります。米国のコンテンツマーケティング研究でも、定期的に専門的知見を提供するメディアほど、メール登録率や再訪率が高い傾向が示されています。検索流入を入口としつつ、ニュースレターや会員化へと自然に接続する設計が求められます。
結果として、オウンドメディアはマーケティング施策の一部ではなく、企業のデータガバナンスとブランド信頼を同時に担保する基盤へと進化します。ポストCookie時代に成果を出すメディアとは、テクノロジーではなくコンテンツの質と誠実さによって、読者から選ばれ続ける存在なのです。
ステルスマーケティング規制が現場に与えたリアルな影響
2023年10月に施行されたステルスマーケティング規制は、2024年に初の措置命令が出たことで、現場にとって「知っている法律」から「無視できない現実」へと変わりました。特にオウンドメディア運用では、これまで黙認されてきた慣行が一気にグレーからレッドへ移行した点が、心理面・実務面の両方に大きな影響を与えています。
消費者庁が医療法人に対して出した初の措置命令では、割引を条件に高評価口コミを依頼した行為が問題視されました。ここで重要なのは、対象が広告記事そのものではなく、口コミという第三者の表示だった点です。これにより現場では、「第三者の声だから安全」「外部ライターだから問題ない」という認識が通用しなくなりました。
オウンドメディアでも、モニター企画や体験談コンテンツの設計が一変しています。編集部が構成案やトーンを細かく指定した場合、それだけで事業者関与と判断される可能性があるためです。結果として、企画段階から法務確認を挟まないと進められないケースが急増し、制作スピードの低下を実感する担当者も少なくありません。
| 項目 | 規制前の一般的運用 | 規制後の現場変化 |
|---|---|---|
| 体験談記事 | 謝礼ありでも明示せず掲載 | 広告明示か企画自体を中止 |
| 社員SNS拡散 | 暗黙の業務協力 | 自主性の証明や表記必須 |
| 外部ライター | 編集部主導で構成指定 | 関与範囲の文書化が必要 |
一方で、すべてがネガティブな影響ではありません。広告であることを明示した記事の方が、かえって読者からの信頼を得やすいという声も増えています。日本広告審査機構や消費者庁の考え方に沿い、主体と意図を開示したコンテンツは、炎上リスクが低いだけでなく、エンゲージメントが安定しやすいと編集現場では評価されています。
現場レベルで最も大きな変化は、チェック体制そのものです。表現単位の確認から、企画背景や報酬設計まで含めた確認へと範囲が拡張しました。これは負担増に見えますが、「なぜこの企画が広告に当たらないのか」を説明できる状態を作ることで、結果的に法務との無用な差し戻しが減ったという事例もあります。
ステルスマーケティング規制は、現場にブレーキをかけただけではありません。広告と編集の境界を言語化し、説明責任を前提とした運用へと進化させた点で、オウンドメディアの成熟を促す圧力として機能し始めているのです。
薬機法・景表法がコンテンツ表現に与える制約とは
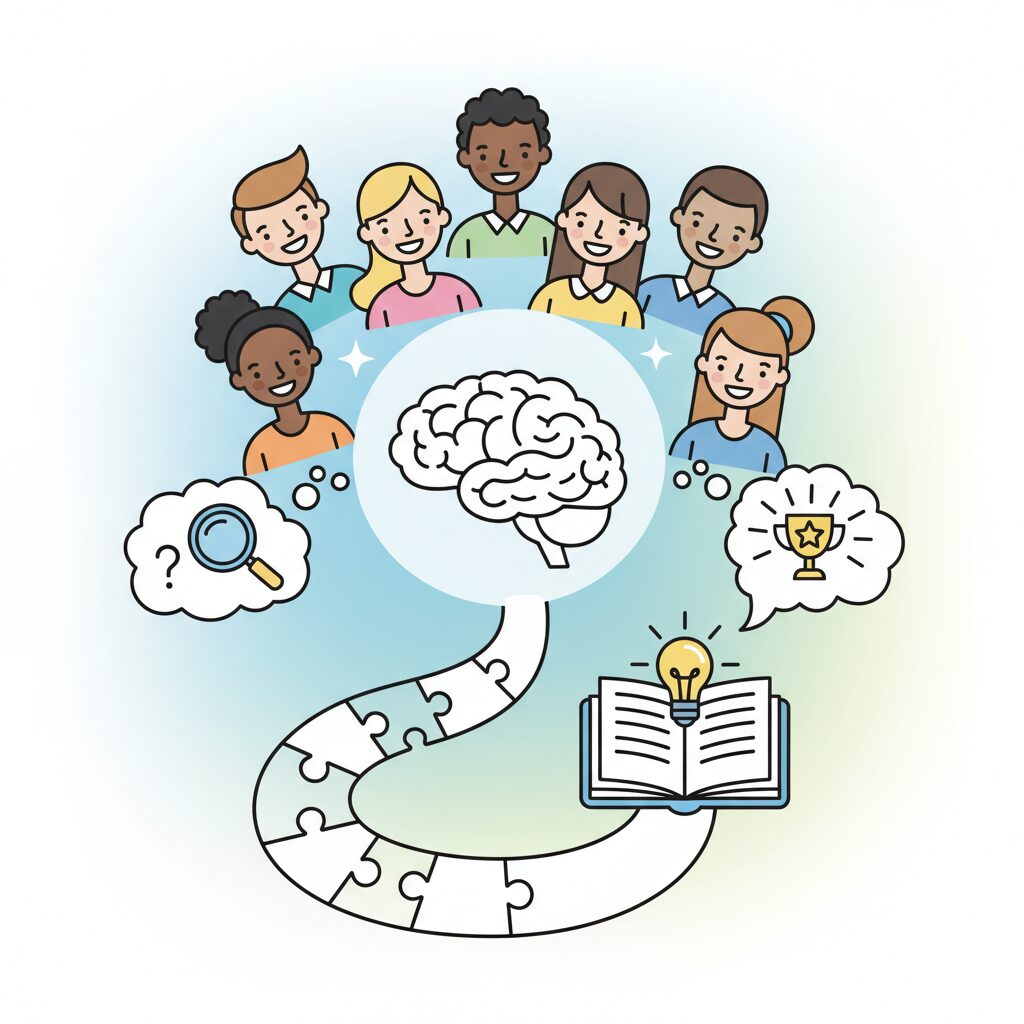
薬機法と景品表示法は、オウンドメディアの表現設計に直接的な制約を与える代表的な法律です。特に健康、美容、医療、食品分野を扱うメディアでは、読者の期待を高める表現ほど違法リスクが高まるという構造的な緊張関係が生まれます。
薬機法では、医薬品や医薬部外品、化粧品、さらには健康食品についても、身体の機能や疾病の治療・予防を想起させる表現が厳しく制限されています。厚生労働省や消費者庁の見解によれば、「効果がある」「改善する」といった断定的・機能的表現は、承認を受けていない限り違法となる可能性があります。
この制約は、エビデンスの有無とは無関係です。たとえ研究論文や専門家の見解を引用しても、商品そのものの効果効能として読者に受け取られる書き方をすればアウトになります。そのため実務では、成分の一般的な性質や、使用感、ライフスタイル提案といった間接的な語り口が重要になります。
| 観点 | 許容されやすい表現 | リスクが高い表現 |
|---|---|---|
| 健康食品 | 健康維持をサポートする | 血糖値を下げる |
| 化粧品 | 肌を整える、うるおいを与える | シミが消える、若返る |
一方、景品表示法は「事実よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示」を禁止します。2023年に明確化されたステルスマーケティング規制は、2024年に初の措置命令が出たことで現実的なリスクとなりました。消費者庁によれば、第三者の体験談であっても、事業者が関与していれば広告表示と判断されます。
オウンドメディアでは、導入事例やユーザーの声を掲載する機会が多いですが、対価提供や編集関与の有無によっては、広告であることの明示が不可欠です。「自然な記事に見せたい」という編集判断が、逆に法令違反を招く点は注意が必要です。
重要なのは、これらの法律が単なる禁止事項ではなく、表現の設計図を与えていると捉えることです。レッドラインを正確に理解すれば、安全な範囲で最大限に読者の関心を引く表現を意図的に設計できます。制約を理解しているメディアほど、結果的に表現の自由度は高まります。
生成AI時代に避けて通れない著作権リスクの考え方
生成AIの活用が前提となった現在、オウンドメディア運営において著作権リスクは避けて通れない論点です。重要なのは、生成AIを使うこと自体が直ちに違法になるわけではなく、**どの段階で、どのように使うか**によってリスクの性質が大きく変わる点です。ここを誤解すると、必要以上にAI活用を萎縮させるか、逆に無自覚な侵害を招くことになります。
文化庁が公表した「AIと著作権に関する考え方」によれば、著作権侵害の判断軸は従来と同じく類似性と依拠性です。生成された文章や画像が、既存の著作物と表現上の本質的な特徴を共有しているか、そして既存著作物にアクセス可能な状況下で作られたかが問われます。**利用者が元ネタを知らなかったとしても、客観的にアクセス可能であれば依拠性が否定されない可能性がある**という整理は、現場にとって非常に実務的な示唆を含んでいます。
特にオウンドメディアで問題になりやすいのは、生成物の利用段階です。日本の著作権法では、情報解析目的での学習は一定条件下で認められていますが、公開コンテンツとして使う段階では別次元の注意が必要になります。例えば、アイキャッチ画像を生成AIで作成する際に「有名キャラクター風」「著名イラストレーターの画風で」といった指示を出す行為は、依拠性が強く推認され、侵害リスクが一気に高まります。
| 利用シーン | 主なリスク | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 文章生成 | 既存記事との高い類似性 | 公開前にコピーチェックを行い、構成や表現を人の手で再設計する |
| 画像生成 | 画風・キャラクターの模倣 | 特定作家名や作品名を想起させる指示を避ける |
| 要約・翻案 | 実質的な転載扱い | 主従関係を明確にし、引用要件を満たす |
ここで押さえるべき視点は、生成AIを「自動執筆ツール」として扱わないことです。**AIは下書きや発想補助にとどめ、最終的な表現責任は人が負う**という運用ルールを明確にすることで、著作権リスクは大きく低減できます。実際、国内外の大手メディアでは、AI生成物に対して人間による編集と類似性チェックを必須工程として組み込む動きが進んでいます。
また、著作権リスクは法的問題にとどまらず、ブランド毀損とも直結します。仮に訴訟に至らなくても、「他人の作品を真似たメディア」という評価が広がれば、読者からの信頼は一気に失われます。生成AI時代の著作権対策とは、単なる防御ではなく、**オリジナリティを組織としてどう担保するかという編集戦略そのもの**だと捉えることが重要です。
『法務が怖い』が生まれる組織構造と心理的要因
オウンドメディアの現場で「法務が怖い」という感情が生まれる背景には、個人の知識不足以上に、組織構造そのものが抱える歪みがあります。多くの企業では、マーケティング部門と法務部門が異なる評価軸で動いており、この非対称性が心理的な緊張を常態化させています。マーケティング側はスピードや成果を求められる一方、法務側はリスク最小化を使命としています。この前提が共有されないままチェックが行われると、現場には「どうせ止められる」という学習性無力感が蓄積していきます。
特に問題なのは、責任の所在が曖昧な組織ほど、リスク判断が個人に押し付けられる点です。記事が炎上した場合の説明責任や意思決定プロセスが明文化されていないと、担当者は自分を守るために最も無難な表現を選びます。これは心理学でいう損失回避バイアスに近く、得られる成果よりも、失う可能性のある評価や立場を過大に見積もる状態です。Voicyが実施した調査で、ハラスメントを恐れて指導を控えた経験が8割に達したという結果は、この萎縮が個人ではなく環境要因であることを示しています。
さらに、日本企業特有の減点主義的な人事評価も「法務恐怖」を増幅させます。攻めた記事で成果を出しても評価は緩やかにしか上がらない一方、法的トラブルや炎上が起きた場合のマイナスは一気に顕在化します。この非対称なインセンティブ構造のもとでは、挑戦しないことが最適解になってしまいます。
| 観点 | マーケティング部門 | 法務部門 |
|---|---|---|
| 主なKPI | 公開スピード・成果 | リスクゼロ・事故防止 |
| 失敗時の影響 | 個人評価への直撃 | 組織全体の問題化 |
このような構造の中で、法務チェックは「相談すれば助けてくれる存在」ではなく、「最終的に否定される関門」として認識されがちです。結果として、チェック前から表現を弱め、企画段階で挑戦的なテーマを避けるセルフ検閲が起こります。これはコンプライアンス意識が高いのではなく、単に心理的安全性が低い状態です。
「法務が怖い」という感情の正体は、法律そのものへの恐怖ではなく、組織内で孤立することへの恐怖です。この恐怖を放置したままでは、どれほど優れた編集方針や戦略を掲げても、現場は動きません。まず向き合うべきは、法的知識以前に、誰がどこまで判断し、何が起きたら組織としてどう守るのかという心理的・構造的な設計なのです。
攻めと守りを両立するためのリスクベース運用という発想
オウンドメディアで攻めと守りを両立させる鍵は、すべてを一律に管理しようとしないリスクベース運用の発想にあります。リスクをゼロにすることを目的にすると、表現は無難になり、結果として読まれないメディアになります。一方で、リスクを理解し、コントロール可能な範囲に限定すれば、攻めるべき領域に経営資源を集中させることが可能になります。
この考え方は、金融や医療の世界ではすでに常識です。すべての取引や処置を同じ厳しさで扱わず、影響度と発生確率で優先順位を決めます。オウンドメディア運用でも同様に、記事ごとにリスクの重さを見極めることで、スピードと安全性を同時に確保できます。
| 観点 | 低リスク | 高リスク |
|---|---|---|
| 主な内容 | 事実報告・告知・レポート | 効果訴求・比較・評価 |
| 想定影響 | 限定的 | 法的・社会的影響が大きい |
| 求められる対応 | 現場判断で迅速公開 | 専門部門との事前協議 |
重要なのは、この線引きを感覚ではなく、組織の共通言語として定義することです。消費者庁が示すステルスマーケティング規制や、薬機法における虚偽誇大広告の判断基準は、守るべき最低ラインを具体的に示しています。このラインを正確に理解していれば、それ以外の領域で過度に萎縮する必要はありません。
例えば、ファーストパーティデータ活用を目的としたコンテンツでは、個人情報保護や外部送信規律がリスクの中心になります。ここをクリアした上で、読者の課題に深く踏み込んだ分析や独自見解を提示すること自体は、リスクではなく競争優位です。GoogleのサードパーティCookie廃止が進む中、価値ある情報提供による信頼獲得こそが最大の攻めになります。
また、文化庁が整理した生成AIと著作権の考え方も、リスクベース運用の好例です。学習段階と利用段階を分けて考え、公開前に類似性を確認するプロセスを入れれば、AI活用そのものを止める必要はありません。危険なのは技術ではなく、無自覚な運用です。
リスクベース運用が組織にもたらす最大の効果は、心理的安全性の向上です。どこまでが許容範囲かが明確になれば、担当者は不要な自己検閲をせずに済みます。Voicyの調査が示したハラ萎縮と同様、不明確なルールこそが人を黙らせるのです。
攻めと守りを両立するとは、危険を避けることではなく、危険を理解した上で扱うことです。リスクを分類し、管理し、許容する。この運用が定着したとき、オウンドメディアは初めて、信頼を損なわずに市場で存在感を発揮できるメディアへと進化します。
編集ガイドラインとチェック体制が成果を左右する理由
編集ガイドラインとチェック体制は、単なる運用ルールではなく、オウンドメディアの成果を直接左右する経営インフラです。ガイドラインが曖昧な組織ほど、現場は過度に萎縮し、結果として無難で読まれない記事が量産されます。逆に、判断基準が明文化されているメディアでは、挑戦的なテーマであってもスピーディに意思決定が進みます。
消費者庁や文化庁が示す近年のガイドラインを見ても、法規制そのものより問題視されているのは「組織としての管理体制」です。景品表示法のステマ規制における措置命令事例でも、個々の表現より、チェック不在やルール不備が重く見られました。編集ガイドラインは、違反を防ぐための禁止集ではなく、適法に攻めるための判断軸です。
特に重要なのが、編集部と法務・広報が同じ地図を見ている状態を作れるかどうかです。トンマナ、想定読者、許容される主張の強度が言語化されていないと、法務は最悪ケースを前提に判断せざるを得ません。その結果、現場は「どうせ通らない」という学習性無力感に陥ります。
| 項目 | ガイドライン未整備 | ガイドライン整備済み |
|---|---|---|
| 編集判断 | 担当者ごとにばらつく | 基準に沿って迅速 |
| 法務チェック | 網羅的で時間がかかる | 論点が明確で短時間 |
| コンテンツ品質 | 無難で均質化 | 独自性と一貫性が担保 |
チェック体制において成果を分けるのは、多重チェックの有無ではありません。重要なのは、どのリスクを、誰が、どの段階で見るかが設計されていることです。編集段階で事実確認と表現の妥当性を担保できていれば、法務は最終的なレッドライン確認に集中できます。チェック工程の役割分担が明確なほど、全体のスピードと精度は上がります。
実際、国内外の成功しているオウンドメディアでは、編集ガイドラインを外部ライターにも公開し、セルフチェックを前提とした運用を行っています。ロイターや日経が編集指針を公開しているのも、品質を属人化させないためです。基準が共有されていれば、チェックは対立ではなく共同作業になります。
編集ガイドラインとチェック体制は、守りのために設けるものではありません。攻めた企画を安心して世に出すための安全装置です。この装置が精緻であるほど、現場は迷わずアクセルを踏めるようになります。
先進企業の事例に学ぶオウンドメディア運用の突破口
先進企業のオウンドメディア運用に共通する突破口は、奇抜な企画や強い言葉選びではありません。法務・編集・マーケティングを分断せず、最初から統合された運用設計を行っている点にあります。多くの企業がコンプライアンスを理由に足踏みする中で、成果を出している企業ほど、ルールを前提条件として創造性を解放しています。
代表的なのが、調査報告書内でも触れられているソフトウェア開発C社の事例です。同社は記事をリスクレベルで分類し、すべてを法務チェックに回す従来型フローを見直しました。その結果、ニュース性や専門性の高い記事をスピーディに公開できる体制を構築しています。攻めた内容を止めないために、止めるべきポイントだけを明確化したことが転換点でした。
| 項目 | 従来型運用 | 先進企業の運用 |
|---|---|---|
| 法務の関与 | 全記事を事後チェック | 高リスク記事のみ事前関与 |
| 公開スピード | 平均数週間 | 即日〜数日 |
| 編集判断 | 担当者依存 | ガイドラインに基づく裁量 |
また、noteが公開している編集・クリエイター向けガイドラインも、先進事例として多くの企業に参照されています。広告である場合は主体と便益を明示し、読者にとっての価値を先に示すという考え方は、景品表示法のステマ規制と真正面から整合します。隠さない、誤魔化さない姿勢そのものがブランド価値になるという発想は、企業オウンドメディアにもそのまま応用できます。
さらに、サイボウズが公開している市民開発ガイドラインは、部門横断ルールの好例です。ITや法務が「禁止する側」ではなく、「安全に試せる環境を整える側」と定義されており、マーケティング施策も同様の思想で運用されています。これは、オウンドメディアにおいても法務をブレーキではなくガードレールとして扱う実践例だと言えます。
これらの企業に共通するのは、「炎上しないこと」ではなく「挑戦を止めないこと」を目的にルールを設計している点です。消費者庁や文化庁が示す公式見解を正確に踏まえた上で、その範囲内でどこまで表現できるかを組織として合意しています。結果として、均質化を避け、記憶に残るオウンドメディア運用を実現しているのです。
参考文献
- 消費者庁:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
- 商事法務ポータル:消費者庁、医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令――ステルスマーケティング規制に基づく初の事例
- 文化庁:AIと著作権に関する考え方について
- Braze:Cookie規制とは?現在の状況やこれから起こる影響や対策・注意すべきこと
- WACUL LAB:マーケティングDX部門に関する実態調査
- 株式会社Voicy:ハラスメントを気にして厳しいことを言えない『ハラ萎縮』の実態調査